トピックス
写真家・六田知弘の近況 2006
展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週水曜日更新)。
過去のアーカイブ
- 2006.12.27 2006年最後のトピックス
-
この世に生をうけてついに半世紀。今年は、私にとってはさまざまな面で大きな節目 の年となりました。特に仕事と健康面でそのことを強く感じた年でした。本当に多く の人達との出会いがあり、人々に励まされ、助けられて、石ころだらけの山道をあえ ぎながらも、ここまで登ってきたという感じです。そして今、いくつ目かの大きな峠 に差し掛かっているところのように思えるのです。足は痛み、腰は軋みます。勿論ま だまだ頂上なんて見えるはずもありません。でもこの薄暗い樹木の茂みの向こうに は、視界がパーッと開けた明るい場所に出られるような予感もします。そこまで行っ たら荷物を降ろして、地面に座り、景色を眺めながら一休みしようと思います。いま はただ、それを期待して、ゆっくりとでも、一歩一歩足を前に、上に運んでいくしか ありません。
来年も皆様にとって良い年でありますように。
(この欄は、次回は一回お休みで、新年は第二週からはじめます。)(六田知弘) - 2006.12.20 北陸本線筒石駅

息子と二人で新潟県の筒石(つついし)と親不知(おやしらず)に行ってきました。
息子は、前にも書きましたように熱心な鉄道ファンですが、今回は列車の写真を撮る 「撮り鉄」というより、列車に乗って旅をする「乗り鉄」に付き合いました。
筒石駅は、青函トンネルができるまでは、日本で唯一の、トンネルの中にある駅で、 私は30年前の学生時代、日本中を独りで旅して歩いていたころに、一度だけ立ち 寄ったことがありました。ホームは山をぶち抜いたトンネルのなかにあって、そこか ら改札口のある山上まで延々とタイムトンネルのような勾配のある歩行者用のトンネ ルを登っていかなくてはなりません。息子は、去年、学校の鉄道研究部の合宿で数人 の同級生とこの筒石駅を訪れました。そのときの印象が強かったのと、たまたま私が 昔行ったことがあるということで、もう一度、父子で訪れてみたくなったのだそうで す。
駅は、ホームと登りのトンネルとの間に列車通過時の風を避けるために設置されたア ルミの扉や、その脇に置いてある列車待ちのためのプラスチック製の椅子、そしてト ンネルの天井の薄暗い蛍光灯と張り巡らされた黒い電線など、30年前とほとんど変 わっていないようにおもわれました。山上の改札口を出て、真新しい北陸自動車道の 巨大なコンクリートの橋脚をくぐって、十数分ほど下っていくと筒石の小さな集落の すぐ上に出ます。漁港があります。その脇の海岸沿いに150メートルもあるような 細長い瓦屋根の建物が見えます。よく見ると、そこには小さな漁船の一部や黒い魚網 のようなものもわずかに見えるので長屋のようになった船小屋なのでしょう。これも 屋根瓦は葺き替えているでしょうが、建物自体は以前来たときとあまり変わっていな いように思います。12月にしては暖かいおだやかな風をうけながら二人でその漁村 の写真を(息子はフイルムのカメラで、私は、デジカメで)撮ったあと、今度は、逆 方向の列車に間に合うように海から山の上の改札口まで息をきらせて登りました。そ して長いトンネルを写真を撮りながら地底のホームへと下りていきました。30年前 に一人で来たときと同じように。
その夜は、親不知の断崖上にある古びたホテルの海の見える六畳間で、雨の音を聞き ながら、布団をならべて休みました。
息子がいつまで私に付き合ってくれるかわかりません。でも、付き合ってくれるうち は、いろんなところにこうしてカメラをもって出かけて行きたいと思うのです。(六田知弘)- 2006.12.13 李朝白磁瓶

奈良の実家に一本の李朝の白磁の瓶があります。数年前に私が、母に勧めて買わせた ものです。首が曲がり、胴体も腰の下からへたっています。それに口が数箇所欠けて 金繕いもされています。ですからかなり安く手に入れました。でも曲がってはいます が肩から口にかけてまっすぐに伸びた首とその下の柔らかくたっぷりと膨らんだ胴、 そして何より真っ白な素地に透明な釉薬が厚くかかったその肌合いが特別に魅力的な のです。釉薬が特に厚くかかった部分はうっすらと青みを帯び、全体にきれいな氷裂 が網の目のようにかかっています。
私は、実家に帰るといつも棚からその瓶をとりだし、胡坐をかいた膝の上にのせて、 掌でなでたりまわしたり、頬につけてその温度を確かめたりしています。そうしてい ると、何ともいえぬ安らぎを覚えるのです。
人間の感覚と技によって視覚的に完璧な色や形の美をめざすいわゆる鑑賞陶器もいい のですが、一方、このような触覚で感じる美、あるいは、触覚的視覚ともいうような もので味わうやきものの美というものも我々にはたいせつなものとして伝えられてき たのだと思うのです。私も歳のせいか、このごろは、こうしたものにじわじわとより 強く引かれるになってきたようです。(六田知弘)- 2006.12.06 高幡不動の裏山のキツツキ
-
2~3日前、いつものように高幡不動の裏山を落ち葉を踏みながら駅に向かって歩い ていたとき、先の木々の間から コッ、コッ、コッ、コッと結構響くいい音が聞こえ てきました。すぐ、これはキツツキが木の幹をつつく音だとわかりました。高幡不動 の裏山ではいままでにもキツツキの音をときどき聞くことがありました。しかし、今 回のはそれとはちょっと音が違います。いままで聞いたのは、コゲラというスズメく らいのちいさなキツツキが出すココココココココというわりと小さくて早く連続する 音だったのですが、今回のはもっと大きな、音の間隔も少しあいたものでした。これ はコゲラよりはもっと大型のキツツキに違いないと思い、あたりの木々を探しまし た。そして、けっこう容易にその姿を見つけることができました。しかしその姿は、 私がそれまで頭に描いていたてキツツキのイメージとは随分違っていました。逆光で よくは見えなかったのですが、体色は斑になった灰褐色で普通のキツツキのように白 と黒の縞模様ではなく、また、頭に赤や黒の帽子を被ったような部分もありませんで した。それに、嘴も長く鋭いものではありません。しかし、確かにそいつは木の幹に 足のつめをひっかけて地面に対して垂直の姿勢でくちばしを幹に打ちつけて穴を開け ようとしているのです。私は、ヒヨドリがキツツキのまねをしているんじゃないかと 結構本気で思ったほどでした。あとで、図鑑を見てみるとおそらくあれは、アリスイ というキツツキの一種だろうということがわかりました。アリスイは名前が示すとお り主に蟻を食べて、木の穴を巣とし、北海道や東北で繁殖して、冬には九州まで移動 するのだそうです。お不動さんの裏山で見かけたのは、九州への渡りの途中に立ち 寄ったものだったのかもしれません。(六田知弘)
- 2006.11.29 東雲し雪図
-
浦上玉堂の「東雲し雪図」(とううんしせつず)を見てきました。まさに神の手によ る作品に思えました。玉堂が一杯の酒を飲み干して、筆を持って紙に向かったその瞬 間、神なるものがその腕にのり移り、玉堂自身も予想もしなかった稀有なるものに仕 上がった。そんなことが実際あるものだと思います。玉堂のほかの作品も先週この欄 に書いたようにすごいものなのですが、これはまた、別格です。人の手をはるかに越 えて、まるで大宇宙の意志がこれを描かせたとでも言えると思うのです。だからこ そ、この絵の中にその大宇宙の布置のようなものを感じるのです。実はこの絵の前に 立った時、私は、ついついこんな子供じみた空想に浸ってしまったのです。一羽の鳥 となって凍てつく風を顔面にうけながら、この冬景の中を上へ下へと自由自在に飛び 渡り、終いに凍えて向こうの暗い雪山に頭から突っ込んで、消えてしまってもいいの だと。
この「東雲し雪図」は、私にとって最も重要な日本の絵画のひとつだということは、 ずっと前から変わりません。(六田知弘) - 2006.11.22 浦上玉堂展
-
千葉市美術館で開催中の浦上玉堂展に行ってきました。
私にとってこれほど印象に残った展覧会はいまだかつてないように思えます。会場に 一歩踏み入れ、正面の絵の前に立った瞬間、バッと鳥肌が立ち、背中から後頭部に高 圧の電流が走りました。いきなり「気」の一撃をくらった感じです。私はしばらくそ こから動くことができず、頭はしびれ、目蓋からあふれ出ようとする涙をこらえるの に精一杯でした。
以前から玉堂には特別な思いがありましたが、今回その凄さをあらためて思い知りま した。
実際の風景を写生したのではなく、玉堂の心のうちの風景を描いたにもかかわらず、 なぜこれほどまでの確固たる眼差しとリアリティーを感じさせるのでしょうか。宇宙 まで突き抜けるような澄明な目の力と筆力にピーター・ブリューゲルにも似たものを 感じるともいえます。玉堂の作品に向かうとたちまち画中の人や鳥や風となります。
川や木々の音を聞きながら渓流にかかった木橋を渡る人になり、谷間の空間を風を きって飛び回る鳥になったりするのです。今回そんな玉堂の作品が百点以上集まりま した。到底一度では味わいきれません。会期の後半には、あの有名な「東雲し雪図」 や出光美術館所蔵の「じゃくじ籠煙図?」(玉堂の四字漢字の画題は難しい)も出品 されるので何としても時間をつくって再度千葉まで行こうと思っています。
いまだに私の脳内には、あの時分泌されたドパーミンによる心地よいしびれのような 高揚が残存しているようです。
この展覧会を企画された岡山県立美術館と千葉市美術館の担当学芸員の方々にこころ より感謝したいと思います。(六田知弘) - 2006.11.15 鉄道写真
-
先の日曜日、気分転換に、埼玉県の本庄と群馬県の水上に、鉄道の写真を撮りに行っ てきました。といっても私には、鉄道写真を撮る趣味はなく、息子にくっついて行っ たのです。息子は、中学で鉄道研究会に入っていて、今は、なによりも鉄道写真のこ とで頭がいっぱいのようで、休みの日には必ずと言って良いほど朝早く起きてどこか に「撮り鉄」に出かけます。その日も4時半に私をたたき起こし、早朝というよりま だ夜中の道を、最寄のJRの駅へと向かいました。3回電車を乗り換えて、8時前に 上越線の本庄駅に到着。そこから線路沿いに超早足で歩くこと約45分。わが子の体 力がついた事を喜び、それと同時に自分の体の衰えを苦々しく思いながら、やっと第 一の撮影ポイントに着きました。そして、そこで目にしたものはポイント近くの堤防 や道路に並ぶ驚くべく数のマイカーの列、そして、線路に向かってずらっと並んだカ メラの砲列でした。私がかつて仕事で経験した報道の現場をはるかに凌ぐ数でした。 ざっと見て200人はいたでしょうか。年齢的には、中学生から60代と思われる人 まで様々ですが、想像していたよりはるかに大人の比率が高く、約5分の4が大人で した。そして女性は一人もおらず、ことごとく男性でした。(考えてみると、幼児の ころから電車は男の子、人形は女の子と相場は決まっているようですが、それも不思 議と言えば不思議です。)そのポイントでは近いうちに廃車になるという旧国鉄タイ プの電気機関車とムーミン型の機関車が通過するのを待ち構えて、ほとんど皆同じ場 所から、いっせいにシャッターを押していました。
その後、息子と私は、さらに上越線で北上し、群馬県の水上のひとつ手前の上牧とい う駅に行きました。ここでは、奥利根号という懐かしの蒸気機関車D51が走るのを撮影 できるのです。息子にとっては、ほんものの蒸気機関車を見るのははじめてで、随分 意気込んでいるようで、線路の間際の、うまく行けばかなり迫力のある写真が取れそ うな場所に駅から一目散に向かっていきました。私も息子のデジカメを借りて遠くか らその姿をねらってみることにしました。あいにく、みぞれ交じりの氷雨が降ってき て、あたりはかなり薄暗く、走る汽車の撮影には厳しい状態です。しかし、気温が低 く、湿っているため、その分蒸気機関車が噴出す湯気や煙はよく見えるはずです。待 つこと50分。遠くからポーッという汽笛の音がきこえたかと思うと、樹木の間から 白い煙が向こうのほうから近づいてきます。そして間もなく真っ黒な車体が現れまし た。私にとってもかれこれ40年ぶりに見る蒸気機関車の雄姿です。「美しい」とあ らためて思いました。私は遠くから、数人の大人たちに混じって、走り抜ける汽車の 間際からねらっているわが子の影を、車輪の下から噴き出す真っ白い蒸気をバックに カメラにおさめました。息子はいい写真、撮れたのかな。(六田知弘) - 2006.11.08 獅子の香合
-

時々小さな獅子の香合をとりだし、掌にのせてみます。高さも幅も奥行きも5センチ 半ほどで、丸くてころころしています。ひよこ饅頭というものがありますが、あれの 頭を獅子に変えたような形だと考えていただければよいかと思います。胴には二本の 前足と振り上げたふさふさとした尾っぽがついていて、肩には首輪を表したのか数珠 つなぎの塁座があります。そしてそのうえに牙をむきだした獅子頭形の蓋がのってい ます。といっても結構愛嬌のある、かわいい顔つきをしています。底面を除いた全体 に透明釉がかけられ、目や尻尾の一部に鉄斑が施されています。美濃や瀬戸の焼き物 に詳しい方に見てもらったら、これは、江戸初期の美濃のもので、とても珍しいもの だとのことでした。私はこの香合のなかに、1センチ角に切った伽羅の断片をいれて います。獅子頭の蓋をとるとき、身と蓋とが擦れ合い心地よい音がして、ほのかな伽 羅の香りと共鳴します。勿論わたしが持ちえるものだから、高価なものではありませ ん。しかし、400年も前につくられたものが、今私の元にきて、静かに心を和ませ てくれる。手にとって指でなでていると、私のところに来るべくして来たような、不 思議な縁のようなものを感じるのです。(六田知弘)
- 2006.11.01 「仏像 一木にこめられた祈り」展
-
東京国立博物館で開催中の「仏像 一木にこめられた祈り」展を見てきました。
タイトルの通り、ブロンズや塑像ではなく木製の仏像、それも一木彫の仏像を集めた もので、唐からの将来の檀像や奈良時代のものからはじまり、平安の貞観仏や東北地 方で多く造られた鉈彫のもの、そして江戸期の円空や木喰のものまで時代を追って見 渡せるようになっていました。私はあらためて日本人の「木」、ひいては自然に対す る特別な関わり方を知らされた思いがしました。
会場を見て印象に残ったことはそのコンセプトや展示されているものの質の高さもさ ることながら、展示品の見せ方、特にライティングと配置の良さがあります。前面か らの照明の当て方がそれぞれの仏像のツボを押さえてされていたことと、バックから 布越しに柔らかい光を入れることによってより立体感をもって見せるという工夫がさ れていました。そして、隣との距離が程よくとってあるため、一つ一つの仏像をほか のものに邪魔されることなく注視することができたのです。
仏像は、本来は博物館などで見るものではなく、やはり寺院のその祈りの空間で観る べきだと思います。しかし、こうした展示場で彫刻として見てその精神を知ることも、 ひとつのまじめな接し方だと思います。
この展覧会の後半には向源寺の十一面観音像が始めて寺外で展示されるので、わたし は、もう一度見に行くつもりです。学生時代に一人で湖北の向源寺を訪れて、この十 一面観音を仰いだときの強い印象と今回接するときの印象にどんな違いがあるのか、 それとも無いのか、ちょっと楽しみにしています。(六田知弘) - 2006.10.25 ロマネスクの光

ここのところ連日、ロマネスクの写真のプリントをしていました。そのなかでもフラ ンス プロヴァンス地方のル・トロネ修道院はモノクロにしました。ル・トロネは、 ご承知の方も多いと思いますが、シトー派の代表的な建築で、装飾をできるだけ排除 した非常にストイックな感じをうける僧院です。ロマネスク美術というと、誰しも思 い浮かべる柱頭彫刻は、この建物にはほとんどなく、(厳密に言うと参事会室と呼ば れる部屋の入り口の石柱に小さな松ぼっくりの彫刻を見つけたのですが・・・)まし てやフレスコ画などは一切ありません。つまり、建築が「素」のままで存在している のです。それゆえに、この僧院建築そのものが有する簡潔な力強さと静謐さが、われ われに直に伝わってくるのです。
堂内に入ってまず感じるのは、その独特の光です。きわめて暗い堂内に入ったとき、 正面のアプシス(聖職者が礼拝を行う場所)の馬蹄形の小さな3つの窓とその上方の 円形の光取り窓から差しこむ光、というか、丸や馬蹄形のその白い光のかたちに人は、 足を止めます。そこで、我々は、日常とは切り離された異空間にはいったことを知る のです。私は、これまでに、たくさんのロマネスクの僧院を訪ねてきました。そして、 ロマネスクの僧院の光の演出の巧みさにいつも驚かせられます。なかでもこのル・ト ロネなどのシトー派の僧院は、他の装飾が排除されたためになお更その光の演出が効 果を示すのかもしれません。わたしは、この光の意味をよりはっきりと示すためにあ えてモノクロプリントを選んだのです。
薄暗い空間に入ることによって、我々は、自らの内面に目を向けます。そして、その 暗闇に差し込む微かな光に神を感じることもあるのでしょう。そういえば、ル・トロ ネと同じくプロバンスのシトー派三姉妹のうちのひとつ、シルバカーヌ修道院で、一 人のいかにもヤンキー風な身なりをした若者が、薄暗いなかでアプシスに向かってひ ざまづき、約一時間も身動きもせずに祈る姿を見たことがあります。我々の日本には このような自らとそして神と対話できる光を残したた空間は、いったいどれだけ残さ れているのでしょうか。(六田知弘)- 2006.10.18 ミャンマーのキナリ
-

ミャンマー(=ビルマ)の木製のキナリの彫刻を手に入れました。
キナリはキンナリとも言い、わたしが以前からその資料を集めている迦陵頻伽や共命 鳥、ガルーダなどと同じ「人面鳥」の一種です。古代インドやガンダーラから南アジ ア、そして東南アジアへと伝播し、主に仏教寺院やヒンズー教寺院などで仏や神を荘 厳する飛天のような役割で登場する空想動物です。因みにキナリはメスで、オスはキ ナラあるいはキンナラと呼ばれます。
東南アジアではそのキナリやキナラは現在でも生きていて、タイ国王の在位60年の 晩餐会のテーブルの上にもその人形が飾られているのを写真で見つけました。実は、 この木製のキナラと同時にブロンズのキナラの像も手に入れました。このキナラもお そらく何らかの装飾品として作られたもので18から19世紀のもののように思えま す。ひょっとしたら、ビルマ王の食卓を飾っていたものかもしれません。(そんなこ とはないでしょうが・・・。)
さて、木製のキナリですが、高さは25センチほどで、二つの花模様の台座をしっか りと鳥形の足でつかみ、顔は前方を向いて、胸の前で合掌しています。いかにも古い ものらしく黒光りしていて、鼻を近づけるとすっぱいような、香ばしいような、独特 の刺激臭がします。これは、私にとっては、とても懐かしい匂いで、ヒマラヤの民家 に滞在していた時に日常的にかいでいた、あの薪で燻された家の匂いと同じものに思 えました。
聞くところによると、この木製のキナリ像は、比較的高貴な人を乗せる牛車の先端に 付ける飾りで、いわば自動車のジャガーのボンネットの先にある疾走するジャガーの 像のようなものだとのことです。そう考えると、熱帯のまぶしい光にあふれたデコボ コを道を、日除けの傘をさしたヨソイキ行き姿の家族が牛車に揺られている。牛は、 立ち止まることなく時々ボタボタと糞を地面に落としながら、ゆっくり、ゆっくりと 進んでいく。その牛車の先端には、疾走するジャガーではなく、この合掌するキナリ が付いている。
そんなのどかな、そして豊かな情景が目にうかぶのです。(六田知弘) - 2006.10.11 2冊の写真集
-
『神々の残影』、『北回帰線の北』という2冊の写真集が送られてきました。いずれ も沖縄八重山諸島を撮ったもので、前者は1963年、後者はそれからずっと後の1 988年から2001年の撮影です。
ページを開いて、私の魂は、激しく揺さぶられました。そして今まで自分はいったい 何をしてきたのかという思いでいっぱいになりました。
吉田元さん。この2冊の写真集の著者です。吉田さんは去年4月に亡くなられました。 これらの本は、吉田さんがが病床で作られた完璧なダミー本をもとに、残されたご家 族が出版までもってこられたのです。私は、今はまだこの写真集について何も言葉に することができません。ただひとつ、写真というものは、この世に束の間ではあるけ れど「存在」した一人の人間の「たましい」を刻み付けることができる、数少ないメ ディアのひとつだと言うことを改めて確信したということだけは言えるのです。(六田知弘) - 2006.10.04 金銅馬金具とアルカイックスマイル

先日、東京で古墳時代の金銅の馬の装飾金具の一種である杏葉(ぎょうよう)を見る 機会がありました。そして、先週、関西に仕事で行ったついでに奈良県立橿原考古研 究所の付属博物館で、奈良県桜井市出土の金銅杏葉を復元したものと、あの有名な藤 ノ木古墳出土で国宝にしていされている金銅杏葉や鞍金具などを見てきました。
これらは、藤木古墳のものが他のものより一ランク上ではありますが、いずれも当時 としては相当なレベルのものといえます。そして、どれからも中国の南北朝、なかで も北朝の東魏あるいは北斉の匂いが漂いだしていました。つまり東魏や北斉の金銅仏 などの金工品に近い感じをうけたのです。
藤ノ木古墳の金銅の馬具は、以前から中国からの舶来品かそれとも中国からの渡来人 によって日本で作られたものか、議論がありました。私的には、細部の造形に中国の ものと比べて厳しさに欠ける、言い換えれば柔らか味があること。タガネの使い方が ちがうように思えることなどから、後者の説をとります。しかし、いずれにせよ中国 との極めて強い関わりがあるのは間違いありません。
橿原考古学研究所でそれらを見た翌日、私は、現在MIHO MUSEUMにあって、来年、中 国に返還されることになっている、山東省出土で北魏末から東魏のものだとされる、 石造の菩薩立像の前に立っていました。そしてその杏仁形(アーモンド形)の目と口 元がかもし出す アルカイック スマイルに惹きつけられていました。
杏仁形の目→アルカイックスマイル→飛鳥仏→鞍作止利→藤ノ木古墳の鞍金具→金銅 杏葉→北朝→山東半島→青州仏→渡来人・・・・。石仏の神秘的な微笑みを前にし て、私の連想はどんどんと膨らみます。2004年11月17日付のこのTOPICS欄に も書きましたが、やはり私には6世紀から7世紀にかけての日本は、朝鮮半島との関 わりもさることながら、中国、特に山東半島との関わりが、想像以上に強かったので はないかと思えてならないのです。(六田知弘)- 2006.09.27 秋分の日の卵
-
一年に2回、春分の日と秋分の日に、たまごが、平面上で自立するということを聞い たことがあると思います。
先の秋分の日の夕食後、それを思い出して早速冷蔵庫から卵をとりだし、食卓の上で ためしてみました。卵を数回グルグルと回してから左右の親指と人差し指の4本で支 え、そっと息を止めてテーブルの上にのせました。息子はパソコンを、妻は食器を洗 いながら、ときどきチラチラとこちらの様子をうかがっています。5分ほど一個の卵 で試みましたが、全く立つ気配がありません。この卵の形が悪いからだと、別の卵に 取り替えてやってみましたが、これもダメ。三度目の正直と、再度取替え、しっかり と「気」をこめてやってみました。が、どうもうまくいきません。「お父さんヒマだ ねー」と言わんばかりの顔で妻子は私の顔を見ています。そんなはずはない。私の顔 はさぞかし真剣そのものになっていたのでしょう。
実は、真剣になるには、わけがあるのです。だいぶ前、息子によるともう六年も前に なりますが、春分か秋分かは忘れましたが、同じこの食卓で、なんと本当に卵が立っ たのですから! それを妻子は二人とも見ていたし、息子はまだ小学2年生でしたが、 そのことをはっきり覚えているのです。ですから、今回も立たないはずはないのです。 「なぜ春分と秋分の日に卵は立つんだろう?」。息子は、なかなか立たせることがで きないで苦労している父親に、遠慮がちにつぶやきます。「地球の引力の関係かな?」 なんて卵を立たせるのに集中しきっている父はいい加減に答えます。結局、5つの卵 でやってみたのですが、今回はあきらめざるをえませんでした。
はたして、卵が立ったのを再び妻子に見せられる日は来るのでしょうか。。(六田知弘) - 2006.09.20 邯鄲の音色

九州地方に被害をもたらして日本海に去っていった台風13号の影響か、東京多摩地 区は、久しぶりにきれいな夕焼けとなりました。
ほんとうにこんな鮮やかな夕焼けを、このあたりで見ることはそう多くありません。 故郷の奈良では、夏や秋には3日に一度は見られたのですが、空気の澄み具合で違う のでしょうか?
それとも単に私が、夕暮れ時には都心部に出ていることが多く、知らないだけなので しょうか。
その夕焼けに誘われて、2階の窓から写真を一枚撮ってから、いつもより随分早く犬 の散歩に出かけてみました。玄関を出るとすぐに、まるで大火事のように空は燃え上 がり、ちょっと不気味な感じさえうけました。そして、リーリーリーリーリーリーと アオマツムシの鼓膜を圧迫するようなおおきな鳴き声があたりを支配しています。ア オマツムシは、外来種で、私が子供のころには、日本にはいなかったはずです。この 虫は、すがたは日本のマツムシと似ていますが、色は茶色ではなく青緑で、おもに、 街路樹などの葉にとまってマツムシとは似ても似つかぬ大きな声で鳴くのです。そし て、それは人が近づいても全く平気で、その上そこら中の枝で鳴き競います。私は犬 の散歩はいつもは夜遅く行くのですが、そのときはこのアオマツムシの声はそれほど やかましくはなく、その分日本在来のさまざまな秋の虫のかそけき声を聞き取ること ができるのです。一日パソコンに向かって仕事をしていたために少々疲れ気味の私に はこのアオマツムシの鳴き声は強すぎます。犬をせかしてこの頃いつも楽しみにして いる邯鄲(カンタン)の鳴く場所へと、もう赤銅色となって数匹のキクガシラコオモ リが飛び交う空の下を急ぎました。
ルルルルルルルルル・・・・。丘陵の頂近くの住宅地と雑木林が接するところまでく ると今日も、まるで藤原時代の鍍金の鈴二つを掌にのせて、ゆっくりとまわしている とこんな音がしてくるのじゃないかと想像してしまうような、低いけれど張りがある 、妙なる音色が草むらから聞こえてきました。邯鄲です。ここでは、街路樹がないせ いかアオマツムシの声も随分遠く、いつものように心やすまる声を楽しませてくれま した。
子供のころ祖父は私に、西日本にはいないけれど関東から東北にかけてカンタンとい う虫がいて、その声は和歌や俳句に詠まれるほど魅力的である事、そして、中国に「 邯鄲の夢」という故事があることも教えてくれました。もっとも大和の人間である私 の祖父もその鳴き声は実際には聞いたことはなかったでしょうが・・・。
「藤原の鈴をひとつ、いや、ふたつ手に入れたいな。」そして、「中国河北省の邯鄲 という町やそこから近い響同山石窟にも行ってみたい」などとぼんやり考えながら家 にむかうころは、辺りはとっぷりと暮れていました。(六田知弘)- 2006.09.13 ピレネー山中のロマネスクの村 その2
-
ボイ谷につづきアラン谷にも裏切られ、はるばる峠を越えて全く未知の谷まできた私 は、そこでついに探していた手付かずのロマネスクの村々を見つけました。狭い谷筋 に沿って5つの小さな集落が点在し、その集落それぞれに、一つあるいは二つの教会 が存在します。そしてそれらの教会の大半はロマネスク様式なのです。
私は、日没までには宿に戻りたいので、その日は、ロケハンということにして、明日 本格的に撮ることに決め、早足で集落をまわって行きました。小さな車がどうにかこ うにか通れるくらいの、狭い石造りのロマネスクの橋を渡って入るある集落は、迷路 のように路地が入り組み、家は石と太い木材を使った頑丈そうな古いものばかりで、 路地の上を見上げると家と家の二階をつなぐ渡り廊下が作ってあったり、角を曲がる といきなりロバにでくわしたりしました。また、ある集落のはずれには、古びた教会 があって、その外壁にはいかにも質朴な農民らしい一組の裸の男女の浮き彫りが西日 に照らされ、明日の本番の撮影を待っていてくれました。それにしても十軒から多く ても三十軒くらいしかないような小さな集落ごとに、どうしてそれぞれが立派な教会 をもつことができたのか不思議に思います。
この谷には中世のの匂いがあたり一面に漂っているようで、私はその匂いにちょっと 酔っ払ってしまったようです。すれ違うのも難しい狭い谷沿いの道を谷の一番上の集 落から一気に車で駆け下りました。そして、一番下に位置する集落まで来たときに、 私は道の脇に車を停め、急な斜面に張り付いた十軒あるかないかの小さな家並みに目 をやり、その上方の樹木の間から見える教会の塔を見上げました。あれもロマネスク の教会にちがいありません。
いつの間にか日差しはなくなり、あたりは薄暗くなってきました。しかし、日没には まだ少し時間があるはずです。どこからか、羊のメーメーと鳴く声が聞こえてきます。 車を止めたところから、その塔の写真を撮っていると、集落のとっかっかりの家の前 に一人の老人が座っているのが見えました。そのうち、その老人は、ゆっくりと杖を ついて立ち上がり、羊を迎えに行くのか、小さな木橋を渡って山のほうに入っていき ました。
私は、ひとしきり教会の遠景を撮った後、いままで見てきたものとどこかちがう雰囲 気に引かれ、その教会まで登ってみることにしました。幅1メートル半ほどの地道の 坂道を登り、さっき老人が通った小さな沢を逆に渡って集落に入りました。狭い路地 には石畳が敷かれていましたが、湿った陰気な空気がこもっているようでした。その なかを、一匹の痩せこけた黒犬が私を怖がるかのように道の端っこを通り抜けて行き ました。廃屋になってしまった家が多いのか、さっきの老人以外には人の気配も生活 臭も感じません。路地に入ったせいかあたりは、ますます暗くなってきたようです。 私は、こんなところで雨に降られては大変と、教会への道を急ぎました。
息を切らせてたどり着いたその教会は、集落の上方の薄暗い樹林を抜けたところにあ りました。辺りは、雑草が繁茂し、建物の壁もかなり荒れているように見えました。 私は、この教会は、すでに打ち捨てられていると感じました。もう死んだ教会なのだ と。
ますます暗くなってきました。真っ黒い雲が空半分を覆っています。写真は撮らずに もう帰ろうとした時に、ふと教会の敷地内へ通じる壊れかかった木の門が目にはいり ました。私は思わずそこへ駆け寄り、その木戸を引き開けました。そして、息をのみ ました。私の足元には盛土があって、そのまわりは真新しい花で飾られていたのです。 お墓でした。それもごく最近のもののようです。教会の敷地内に墓地があるのはよく 見かけますが、それがあまりにも門の間際の私の足元にあったので、それもあまりに 真新しいものだったので私は、思わずたじろいだのです。見上げると空一面が黒雲に 覆われていて、地響きのような雷鳴が轟いてきました。向こうで稲妻がしきりに走り ます。わたしは、まるで映画の一シーンみたいだと思いながら、お墓にむかって手を 合わせ、壊れかかった木戸を静かに閉めました。そして、降り出した雨に濡れながら 車にむかって駆け下りたのでした。
みなさんも「手付かずのロマネスク巡り」はいかがでしょうか。(六田知弘) - 2006.09.06 ピレネー山中のロマネスクの村 その1
-
先週、スペインピレネー山中のボイ谷の教会群が2000年に世界遺産登録され、 そのころから周辺にリゾートマンションなどか建ち並びすっかり昔の面影がなくなっ てがっかりしたことを書きました。今週はその続きを書こうと思います。わたしは 、ボイ谷の撮影を早めにきりあげ、ボイ谷より少し北方にあるアラン谷にむけて車を とばしました。アラン谷もボイ谷と同じく谷あいに点在する集落ごとに古いロマネス ク教会があることで知られています。車のすれ違いも容易ではない山道を約4時間、 やっとたどり着いたアラン谷は、リフトとホテルが建ち並ぶ一大ウィンターリゾート 地でした。またもや裏切られました。というより私がいまどき、「そこの住人以外は ほとんど訪れることもないような鄙びた山間の集落にひっそりとたたずむロマネスク 教会」というイメージを探したこと自体が間違いだったのだろう。そう考えながらも この谷のもっと奥まで行くとそんな場所があるかも知れないと、ホテルやマンション の間に見え隠れする教会のとんがり屋根を横目に、アラン谷をずんずん上って行きま した。そして、やっと新しい建物群が途切れたところは、アラン谷の最奥部、つまり 「峠」でした。ここを越えると既にアラン谷ではなくなります。ということは、私の 微かな望みも消えうせたということです。車をとめて眼下に見える氷河によって削ら れてできたU字型の美しい谷を眺めながら深呼吸をし、子供にみせてやろうとシャッタ ーを数枚きりました。そうしているうちに、峠の向こう側に行きたくなってきました。 もしかしたら、私が探しているような場所が向こう側の谷筋にあるのじゃないかと。 私は、再び車に乗り込み、こんどは、ヘアピンカーブの連続の下り坂を約1時間、一 挙に駆け下りました。その間、アラン谷とはうって変わってホテルの一軒も小さな集 落一つも見当たりません。そして、やっとたどり着いた戸数20件位のちいさな村の 古びたホテルの一室を確保して、日没までにはまだ時間があると、(スペインの6月 下旬の日没は午後9時半くらいです)ほとんどあてすっぽに脇の狭い谷道を車で上っ て行きました。
そして、ついに見つけたのです。私の探していた手付かずのロマネスクの村々を。
つづく・・・・
(六田知弘) - 2006.08.29 世界遺産
-
先日、テレビのニュース番組で、、国内各地の世界遺産候補地の登録を経済産業省が 後押しするというようなことを報道していました。私はほかの事をしながら聞いてい たので正確ではないかもしれません。間違っていたらご容赦ください。
実は、私は、それを聞いて、少し危惧の念をいだきました。というのは、今年の6月 末に訪れたスペインのピレネー山中のボイ谷の光景が頭をよぎったからです。ボイ谷 はカタロニア地方の西の端、標高2500メートルを超える山々に囲まれ、岩肌をむ きだした険しい谷です。その谷沿いに小さな集落が点在し、それらの集落には、必ず といってよいほど一つか二つのロマネスク様式の教会があるです。なかでもタウール のサン・クレメンテ教会はその内陣のフレスコ画と高く華麗な塔で有名です。といっ てもそのフレスコ画の実物は、だいぶ以前にそっくりそのまま剥ぎ取られ、現在は、 バルセロナのカタロニア美術館にあって、実際の教会内部にあるものは、そのコピー なのです。そのことは、私も以前から知っていて、それがなかなかボイ谷まで足が向 かなかった理由の一つでした。しかし、もともと私は、ひとのあまり行かない辺鄙な ところが好きなもので、機会があれば人里離れた山間にひっそりとたたずむ教会の建 物だけでも見てみたいと思っていました。そして、今回、フランスから、アンドラと いうピレネー山中の小さな自治国を経て、九十九折の乾いた山道をほとんど一日、延 々と車を駆ってやっとの思いでたどり着いた私の眼前に飛び込んできたものは、信じ られないような景色でした。これじゃまるでテーマパークじゃないか。私は、車を停 めて、思わずあたりを見回し、本物の教会はどこにあるのかと探したほどです。教会 のまわりは、舗装された道路と、広い駐車場、緑の芝生と植栽、そしてなにより、教 会から100メートルほどしか離れていないところまで迫りくる何十棟もの真新しい リゾートマンション。これには、まいりました。実は、ボイ谷は、2000年に世界 遺産に登録されました。そして、そのことがきっかけで、谷も教会も変わりました。 それは、景色を一目見ればわかります。なにもかもが、新しいのですから。経済産業 省が乗り出して、観光振興で地域の活性化を図ろうというのは、わかります。しかし、 そのために世界遺産という制度をイージーに利用するというのどうでしょうか。世界 遺産=観光名所ではないはずです。その次代に引き継ぐ世界遺産の遺産たる所以をし っかり押さえる必要があると思うのです。(六田知弘) - 2006.08.23 バクトリアの女神像
-
紀元前3千年期から2千年期、アフガニスタン北部あるいはトルクメニスタン南部、 いわゆるバクトリア地方出土とされる石製の女神像を撮りました。高さ20センチに も満たないちいさな座像ですが(といっても、この種のものでは最大級でしょう が)、なかなかの迫力でした。最初見せられたときは、単に女性像にしか見えず、な ぜこれを女神像と呼ぶのか実は、すこし訝しく思いました。しかし、撮影台にのせ て、ライティングをしたら、なんという迫力でしょう。地の底に鎮座し、辺りをその 霊的威厳で支配する、まさに若きグレートマザーといったらいいのでしょうか。それ が放つ恐ろしいエネルギーに私はちょっとたじろぎました。まわりに三人の人がいて くれたからよかったももの、わたしひとりでこの像に向っていたら、その力に飲み込 まれていたかもしれないと思うほどでした。そして、正面の撮影を終えて上半身側面 のアップに移ったとき、わたしは、またその印象の変化に驚かされました。なんとい うその麗しい顔立ち。端正な目鼻立ちと薄く小さな耳、そしてうなじから背中にのび る白く、伸びやかな曲線。若き、きれいな、優しい母親の、甘い匂いが漂ってくるよ うです。そういえば、以前このトピックスにも書いた日本の女面を撮ったときにも同 じ経験をしました。どうやら女性には、男には理解しがたい二面性(多面性?)があ るようです。それにしても4~5千年も前にそんなところまで表現し得たということ は、すごいことだと思います。
ところで、グレートマザーといえば精神分析学のCGユングが元型の一つとした概念で すが、それを日本に紹介した臨床心理学者の河合隼雄さんが、先日、脳梗塞で倒れら れたとのニュースを聞きました。私にとって、河合隼雄さんは、その著書から最も影 響を受けた方の一人です。ゆっくりでもいいので回復されることを遠くからお祈りし ております。(六田知弘) - 2006.08.16 クマゼミの大発生
-
先日関西へ行って驚いたことがあります。それは、辺りから聞こえてくる蝉の声が昔 と違うということです。
しゃーしゃーしゃーしゃーというクマゼミの声があたりを支配していて、アブラゼミ やニイニイゼミなどの声が、ほとんど聞こえてこないのです。それらの蝉もいつもと 同じように鳴いていても、あのクマゼミの大きな声にかき消されてしまっているとい うことなのでしょうか?アメリカには17年ゼミという名の17年に一度大発生する 蝉の種がいるということですが、このクマゼミもそうした、大発生の周期に今年は当 たるのかも知れません。そういえば、私の住む東京の郊外でもこのごろときどきクマ ゼミやニイニイゼミの声を聞くことがあります。もともと関東にはそれらの種は、い なかったということですが、やはりこれも地球温暖化の影響なのでしょうか。そうい えば今年は関東でもアブラゼミの鳴き声がいつもよりかなり少ないように思うのです が・・・。(六田知弘) - 2006.08.09 ジャヤヴァルマン7世の彫刻

大阪歴史博物館で「大アンコールワット展」を見てきました。この展覧会はプノンペ ン国立博物館所蔵のクメール時代の石やブロンズの彫刻で構成されており、横浜など 全国を巡回して大阪が最終地だとのことです。流れ落ちる汗を拭きながら会場にたど りつきましたが、行ってよかった。日本では、出土地がはっきりしたクメール美術を 見ることは難しいので、こういう機会はとても貴重です。一概にクメール彫刻と言っ ても6世紀から13世紀までのあいだに、仏教であったりヒンドューであったり、そ れが混交した時代もあったりして、様式的にも結構幅があるのがよくわかりました。
また、ほとんどが砂岩製なのですが、その石質も多様だということも知りました。
数多くのすぐれた展示品のなかでもとくに私が惹かれたのは、コンポントム州大ブリ ヤカーンというところで出土したジャヤヴァルマン7世の頭部の石像です。12- 13世紀に生き、仏教を保護したジャヤヴァルマン7世の彫刻や彼を模した菩薩像は しばしば見受けられますが、この像はそのなかでも間違いなく最高位に位置するもの だ思います。瞑想する若き王の肖像ですが、なんという充実した、自信に満ちた人間 の顔なのでしょう。こんな人間がかつてカンボジアの地に実在したということに驚 き、そしてその精神をこれ以上ないと思えるほどの迫真性をもって表現した石工の力 に私は圧倒されてしまいました。(六田知弘)- 2006.08.02 エジプトのトト神像
-
古代エジプトのトト神像を撮りました。
トト神というのは、クロトキ(黒朱鷺)の姿をした知恵の神様です。一目見て、その 姿に強く惹き付けられました。嘴から尾羽まで全長16センチほどの小さな像なので すが、なんというか、これ以上ないと思われるほど凝縮された造形で、首から先と尾 羽、そして足がブロンズでできていて、胴体は木製で、たたんだ羽の部分は火であ ぶって黒く焦がしてあります。そして、眼には、暗青色のガラスがはまっています。 私はこの小さな像に一個の魂のようなものの存在を感じました。そして、それは、 なんとまっすぐな魂なのでしょう。エジプト美術には、邪悪とまでは言わないとして も、しばしば、あまり触ってはならないと思われるようなものを感じるときがありま すが、これは、そうではありません。作者の魂の投影なのか、これを祀った人の人格 の投影なのか、とにかく正しい知恵を備えた魂の姿を見ているように思えるのです。 2000年以上も前に生きた人の、眼に見えない精神にいまここで、この造形を通じ て接することができるということ。考えてみれば不思議なことです。(六田知弘) - 2006.07.26 見えない紐
-
先日、ある古美術コレクターの方のお宅にうかがい、たくさんのご所蔵品を見せてい ただきました。そして、その方の美的感性にまず感服しました。それとともに私自 身、非常に嬉しくなりました。眼がとっても喜びました。というのも、次から次へと 出してきてくださるもののほとんどが、私の波長にビンビン共鳴するものでしたか ら。いままで多くの方々に素晴らしいコレクションを見せていただき、感心するも の、興味をそそられるもの、欲しいと思うものなどいろいろありましたが、これほど まで、私の感性と同調するものが連続して出てくることは初めてでした。九割までが いつか自分の手元に来てほしいと思ってしまうものでした。というか、それらのもの は、私自身が長い年月をかけて集めたものであるかのような錯覚に陥ってしまう感 じ、と言ったら良いのでしょうか。なかでも、奈良時代の白漆の木鉢などを見ている と、ずっとずっと昔にこの鉢の鈍色の見込みを覗き込み、そのなかで泳いでだことが あるような感覚にとらわれてしまうほどでした。そのコレクターの方と私とは、同じ 古美術愛好家ということだけで、年齢も生きてきた環境も、共通点はほとんどないは ずです。そんな二人の人間を古美術品は見えない紐で結んでくれるのです。(六田知弘)
- 2006.07.19 サン・マルタン・ド・フノヤールの空間で
-
6月16日に写真集「In Praise of Japanese Beauty」の出版記念展が終わりまし た。暑い中、わざわざおいでいただいた方々、ありがとうございました。みなさんと プリントや写真集を見ながらお話しでき、楽しい時間を過ごさせていただきました。
海の日の17日は、この前に撮ってきたロマネスクの写真の整理をしました。日本美 術からイッキに中世ヨーロッパに私のこころは飛んで行き、フランス最南部、スペイ ンとの国境まであとわずか5キロにあるモレイヤス・ラス・イヤスのサン・マルタン ・ド・フノヤールという物置小屋のような小さな教会の、なんとも独特な、土の匂い のするフレスコ画に囲まれた空間を、一日中浮遊し続けていました。(六田知弘) - 2006.07.12 帰国しました。そして写真集できました。

ロマネスクの撮影旅行から帰ってきました。南仏プロヴァンスで車上荒らしにあった り、ほんの少しですが体調をこわしたり、いろいろありましたが、撮影事体は非常に 充実したものになりました。来年の夏には、いままで撮りためたロマネスクの写真を まとめて、みなさんにご覧いただけることと思います。
さて、帰ってきたら例の日本美術の写真集「In Praise of Japanese Beauty-Japanese Aesthetics Through the Lens of Tomohiro Muda」ができあがっ ていました。自分で言うのはおかしいですが、素晴らしい出来ばえです。写真はさて おき、装丁、写真構成、レイアウト、テキストや表の活用、そして一番気になってい た印刷も含め、私が始め考えていたものをはるかに超えるとても良い本になっていま した。この写真集制作に関わってくださった方々、そして、写真撮影においてお世話 になった多くの方々、そして、私にエールを送り、こころの支えとなってくださった 方々に対し、心より感謝いたします。
この写真集の出版記念写真展を東京、南青山の酉福(ゆうふく)ギャラリーで7月 13日(木)から16日(日)の4日間開催します。私は、基本的には毎日在廊する つもりです。大判のプリントとともに、この写真集を是非手にとってご覧いただけれ ばと思います。(六田知弘)
■六田知弘「In Praise og Japanese Beauty」出版記念展
2006年7月13日(木)~16日(日)
午前11時~午後6時 最終日は午後4時まで
酉福(ゆうふく)ギャラリー
107-0062 東京都港区南青山2-6-12 アヌシー青山1階
Tel.03-5411-2900 fax. 03-5411-2901
地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山1丁目」駅下車 徒歩3分です- 2006.06.14 ロマネスクの撮影に
-
6月12日から7月5日までの予定で、ロマネスクの撮影旅行に行きます。
今回は、フランスのブルゴーニュ地方と南のプロバンス地方、そしてフランスとスペインにまたがるピレネー山麓を中心に巡る予定です。
7月1日刊行予定の日本の美術を撮った写真集 「In Praise of Japanese Beauty」制作の最後の詰めの時期と重なり、少々気がかりではあるのですが、ロマネスクの撮影は今の時期を逃すことができません。後は、編集者やデザイナー、印刷所の方々にお任せして、私は、遠くでよい本になるよう神に祈るばかりです。
というわけで、このトピックスも2~3週間お休みさせていただきます。
帰国したら、また、ご報告いたします。乞うご期待。 (六田知弘) - 2006.06.07 冬瓜、葡萄図
-
先日、岡山県立美術館で、久しぶりに鳥肌が立つものと出会いました。
それは、画面の中央に、大きな冬瓜がひとつと、その右手前に小さな葡萄の房が描かれた油絵です。常設展の一番奥の中央に掛けられてあったのですが、遠くから近づいていって、それが目に入った瞬間、バンといきなり殴られたような衝撃で動けなくなってしまいました。しばらくして落ち着いてからプレートを見ると、岸田劉生「冬瓜、葡萄図」とありました。モノの存在の本質を捉える、何と強い眼なのでしょう。この作品は「麗子像」のように良く知られ、高く評価されているわけではないと思いますが、どうであれ、この眼のちからには、私の頭より先に身体全体が反応し、ただただ感心するばかりでした。 (六田知弘) - 2006.05.31
ヒマラヤのシャクナゲ 
まるで梅雨が一ヶ月ほど早まったような鬱陶しい日が続いていましたが、ここ二日は、日が差し、少し汗ばむほどです。私の家の近くでは、ホトトギスが、テッペンカケタカ、テッペンカケタカと昼も夜もさかんに鳴きながら飛び回っています。今現在もその声を聞きながらこれを書いています。
この季節になると、私は、ヒマラヤのシャクナゲを思い出します。
エヴェレストへ行く人は必ず立ち寄るナムチェ村(シェルパ語ではナオジェ)から、西方にはずれ、ターメという村に向かう急峻な山肌につけられた細い道を私はよく通りました。ターメ村の上方にあるターメゴンパ(ゴンパ=ラマ教の寺院)に行くためです。標高は、たしかナオジェが約3400メートル、ターメが約3800メートル、そしてターメゴンパは4100メートル位だったと記憶しています。6月頃だったと思いますが、その道の両側に、いくつものシャクナゲの大群落がいっせいに花をつけるのです。その色も、日本で一般的な赤やピンクはもちろん、白や黄色、薄紫・・・とさまざまで、特に白と黄色は暗緑色の葉の集まりに鮮やかなコントラストをつけて印象的です。途中のタモという小さな集落のあたりでは、大きなシャクナゲがトンネル状に左右から迫ります。雨季が近いこの季節になると、登山やトレッキングに来る人もほとんどなく、地元の人以外でこの圧倒的なシャクナゲの群落を見たひとは、それほど多くはないはずです。
7月になって、すっかり雨季にはいると、シェルパの地は外部との接触はほとんど断たれてしまいます。カトマンドゥから麓のルクラまでの飛行機の運行は10月初旬ころまで中断され、カトマンドゥまでの行き来は、徒歩でしか不可能となります。しかし、乾季ではともかく、雨季のその行程は困難を極めます。私は一度だけそれを体験しましたが、二度とはしたくないものです。雨の中、樹上から、そして足元から血を求めて襲いかかるヒルを払い落としながら、寒さと疲労に耐えて歩かなければなりません。川が氾濫して橋が流され、一日がかりで大回りしたうえに、赤茶色の渦を巻く濁流の上を、竹を互い違いに繋いだものを足場にした仮設のカズラのつり橋に命をあずけ、やっと渡りきったところでも足場はなく、スパイダーマンのごとくに、濁流を背に、岩にはりつき、移動しなければなりませんでした。
ところで、シャクナゲは、ツツジ科の植物で、いわゆる合弁花のため、咲き終わるとそのまま、ぽとりと地面に落ちます。ある日、天空の寺院ともいうべきターメゴンパへの道すがら、白や黄色の花が、樹陰の黒い地面一面に落ちているのを見ました。わたしは、誘い込まれるようにシャクナゲの暗い林に入り込み、息を殺してシャッターを数回きりまいた。そしてそのとき、私の頭にどこからか「散華」ということばが浮かんできたのを覚えています。 (六田知弘)- 2006.05.24 ポンペイレッド

渋谷で開催中の『ポンペイの輝き』展に行きました。入ってすぐの大理石の彫刻の衣の襞の表現には驚かされました。しかし、それより私が引き込まれたのは、いわゆるポンペイレッドが下地に塗られた壁画でした。食堂の内部壁面として描かれたとのことで、高さ2メートル余り、幅4メートルくらいの壁面がコの字形になった大壁画です。その正面中央にはオリーブの冠をかぶり、薄い衣を風に翻し、竪琴を手にしたアポロが描かれています。それは、赤のの空間にあたかも自身が発する磁力によって宙に浮かんでいるように見えます。なんという空間感覚でしょう。
それに見入っているうちに私はいつしか、その描かれた絵よりも、その下地に塗られた赤色、いわゆる「ポンペイレッド」に吸い込まれていきました。このポンペイレッドは何十年か前にローマ市内の建物の外壁に塗るのが流行したと聞きました。私は、かつて、『ローマの壁』を撮影していたときにもしばしば見かけ、その赤い壁に向かって数多くのシャッターをきりました。しかし、実際のポンペイレッドなるものをま近で見るのは初めてです。
その色は、どういう色かと説明を求められたとしたらなんと表現したらいいのか、私はしばし、壁面を前にして、考えました。そして思い浮かんだのは、「大火のときの炎の赤」でした。炎を見ていると、その色は、単純な一色の赤ではなく、明るい赤があり、暗く翳った赤があり、黄色や白色味を帯びた赤もあり、それらの赤が、混ざり合い、重なり合うことによって、あの炎の独特の「赤」がなりたっている。今、目の前にある壁の赤も、そういう「赤」に見えるてきました。
そしてまた、このポンペイの赤い壁に、レンズを向けたい気持ちが、ウズウズと沸いてくるのを感じました。 (六田知弘)- 2006.05.17 フクロウの声

先日、夜の10時ごろ犬を連れて近所を歩いていたら、傍らの森から、いきなり大きな声が聞こえました。 ホーホッ ホーホホーホッ と低いけれども力強い声です。フクロウに違いありません。私は、足を止め、その声の続きを聞きました。一度啼いてから15秒ほどしてまた ホーホッ ホーホホーホッ と繰り返します。声の大きさからしてごく近くで啼いているようです。このあたりでは、毎年今頃の季節には、渡り鳥のアオバヅクがやってきて、もっとずっと高い声で ホホッ ホホ、 ホホッ ホホ ・・・・と2回づつ連続して啼くのをよく聞くのですが、フクロウの声を聞くのはここでははじめてです。5分ほど立ち止まってその声を聞いてから、犬の散歩をつづけ、まだ啼いているだろうかと、帰りも同じ道を通りました。でも残念ながらフクロウは、どこかへ飛び去ったのか、いくら待ってもその鳴き声は聞こえませんでした。その後、毎晩、その道を通るのですが、やはりそれっきりです。
わたしは、なぜだか子供の時からふくろうの仲間がが好きです。たぶんその姿や声がどこか異次元の住人のようなイメージがあるからかも知れません。
フクロウといえば先日まで、東京池袋の古代オリエント博物館で開催されていた、金貨銀貨の展覧会に、古代アテネのふくろう銀貨が展示されていました。
四角い銀にふくろうの姿が押されたもので、世界で最も古いコインのひとつだということです。わたしは、いつもの悪い病気がでて、いつかは、これを一枚手にいれたいものだと、結構真剣に思ったものです。展示品からどれか一枚好きなものをあげるといわれたら、もちろん迷わずそのふくろう銀貨です。古代ギリシャ神話では、フクロウは知恵の女神ミネルバの使いとして、世界中を飛びまわり、多くの情報や知識を集めてくるとされています。
ゴヤの版画集 「ロス カプリチョス」のうちの一枚「理性が眠ればデーモンが目覚める」では、机に伏せて居眠りをする男のまわりに、デーモンを象徴するコウモリとともに、たくさんのフクロウが群がっています。この作品は、私が中学生のころはじめて本で見ておおいに惹きつけられました。
そういえば、いま私が、追い求めているロマネスクの彫刻にもふくろうが時々登場します。正確にはふくろうの一種のミミズクですが。
なかでもフランスとスペインの間に連なるピレネー山脈にほど近い、フランス側にあるサン・ベルトラント・ド・コマンジュのノートルダム聖堂の廻廊の柱頭に一羽、特別魅力的なヤツいるのです。全くの逆光で、光があたらずほとんど誰も気付かないでしょうが、千年近くも、あの場所で、ただだまって我々人間を、陰のほうから見ているのです。こんなことを考えたら、なんだかあいつにまた会いたくなってしまいました。 (六田知弘)- 2006.05.10 シェルパの「馬」の写真

この連休中は、ロマネスクの怪物の写真のプリントにかかりっきりでした。なんせ大量で少々くたびれましたが、やっと終わって今は、心地よい疲れを感じているというところでしょうか。
さて、先週、二十数年前に私が、ネパールヒマラヤのシェルパの村で暮らしていたとき書いたノートがでてきたことをこのコーナーで書きました。読んでいると、すっかり忘れていたことをおぼろげながらも思い出したりしましたが、やはり、というか、不思議にというか、そうした言葉にしたものより、そのとき撮った写真を見ているほうが、私には鮮明に記憶が甦るように思えます。もっともその記憶というのもたいして当てにならない、あとでイメージ化された思い込みだけかも知れませんが・・・。ということで、今回は、私の写真集「ひかりの素足 シェルパ」にもあり、このホームページのgalleryにも掲載している一点、「馬」の写真について思い出すことを、書いてみます。
エヴェレストに通じる山道沿いの標高約2800メートルに位置するシェルパ族の集落モンゾのカミ・スンドゥの家に私は寝泊りさせてもらっていました。カミ・スンドゥは私より2歳ほど年上の青年で、彼とは、東京で出会いました。話をしているうちにネパールの自分のうちに来て、そこをベースにしてシェルパの写真を撮ればよいと言ってくれました。自分の撮影テーマを探していた私は、とても興味をそそられ、その好意にあまえることにしたというわけです。カミ・スンドゥの家は、粗い石を積んでその上に白い漆喰のような泥を塗り、木の板を屋根に葺いて重りの石をのせた、簡単なつくりの二階建てです。一階の木の重い扉を押して中に入ると真っ暗な牛小屋で、松柏類の葉を床一面にクッションのように敷いてあります。そのクッションを踏んで右奥の木の階段を上ると二階の居間になります。居間といっても一部屋だけで、家族全員その部屋で寝起きするのです。そしてわたしも、その部屋で延べ18ヶ月間、皆と寝食を共にさせてもらうことになったのです。電気、ガス、水道もない、そしてもちろん車や電車もない土地で、食物や風習も気候も日本でとはまったく違う、言ってみれば「別の世界」に私は自分の身をおいて、そこから見えてくる何かを写真に写し込みたいと考えたのです。
さて、「馬」の写真です。この写真を初めご覧になったときには、シルエットになっているせいもあって、道にあるこの影は何なのかお判りにならないかもわかりません。が、これは小型ですが、馬なのです。4月になって、ようやく雪が融けてきたころ、わたしは、カミ・スンドゥの家から20分ほど下ったペンガルという集落にあるパサン・ギャルジの家まで何かの用で行く途中で撮ったものです。春の朝日に暖められて、ヒマラヤスギ?が発する甘いにおいがあたりに漂い、氷河から流れ出る水を集めたドートコシ(乳の川)は谷間一面にその川音をとどろかせています。遠くの木橋の傍らにある大きなマニ石(ラマ教の経文が刻まれた路傍の石)のあたりにはじめは、小さくぽつんとひとつの影が見えました。その影はゆっくりこちらに近づいてきます。わたしは、はじめ人影だと思いましたが、そのうち馬だと気づきました。そして、カメラを取り出し、その馬が傍らを通り過ぎるまで数回シャッターをきりました。なんでこんなところに馬が、それも単独でいるのだろうかと訝しく思いました。シェルパの土地では、牛やヤク、そして牛とヤクの混血種であるゾプキョやゾンは良く見るのですが、馬を見たのは、数度だけです。タンボジェゴンパ(ゴンパ=ラマ教の寺院)のリンポチェ(活仏)がターメ村やナオジェ村のマニリムドゥの祭りのときに馬にのってこられたのを見たのと、あとは、クムジュン村かクンデ村のシェルパ(ここでは、山岳ガイドの意)が一頭もっていてそれにのって、山道を颯爽と登っていったのを見ただけです。結局その疑問は解けませんでした。しかし、私は、この写真を見ると、今でも、今朝見たばかりの光景のように、ありありと写真を撮ったその瞬間を思い浮かべることができます。 (六田知弘)- 2006.05.03 黄ばんだノート
-
本棚をさぐっていたら、本の隙間から5冊の黄ばんだで表紙もとれた、A5版のノートがでてきました。わたしが、ネパールヒマラヤのシェルパの村で過ごしたときに、メモ帳として、あるいは、日本の知り合いへの手紙の下書き用として使っていたものです。めくるとページがばらばらとはずれてくるものもあります。これを書いたのは、私が、24歳から28歳までの間ですから、もう、21年から26年も昔ということになります。わたしは、大学を卒業して1年あまり建築写真家の中村保さんのアシスタントをしたあと、中村さんがネパールの写真を撮ってられたこともあって、単身、ネパールに旅立ちました。はじめての海外渡航で不安は全くなかったというと嘘になりますが、それより、単なる撮影の旅ではなく、シェルパの社会のなかに身を置き、しっかりとそれを見据えて写真を撮るのだという、若き意気込みが勝っていたいたように思います。結局、私は、3回で、延べ約18ヶ月間、ヒマラヤ山中ののシェルパの村で生活し、写真を撮りました。今から思えば、やはり、私にとってその後の生きる方向性を決定付けた貴重な体験だったと思います。わたしは、そのとき撮った写真を、写真展と「ひかりの素足 シェルパ」という写真集にまとめましたが、これから、折りをみて、そのシェルパの地での体験を、これらのノートや写真集を参考に、おぼろげになった記憶を紡いでこのコーナーに記していこうと思っています。 (六田知弘)
- 2006.04.26 小さな懸仏

わたしの机の傍らには、以前この欄に書いた信楽の壷とともに5センチほどの小さな懸仏があります。真っ黒で、目鼻も彫られていないズルズルの如来坐像です。でもなんとなくその口元に微笑をうかべているかに見えるのです。おそらく室町ぐらいのものでしょう。もしかしたらこの仏様は、いちど火中されたのかも知れません。高幡不動のござれ市で5年ほど前に買い求めたもので、もちろん市場価値はたいしたものじゃありません。しかしこれも私の傍らにいつも置いておきたいもののひとつなのです。 (六田知弘)
- 2006.04.19 古いポストカード

先日、通りがかりに東京駅の地下街にある古書店に立ち寄ったところ、古いヨーロッパの絵葉書のコーナーがあるのに気づきました。何百枚かの束を探っていると一枚の不思議なものに目が留まりました。それは、コロタイプらしきもので印刷されたセピアいろになった葉書で、平面に丸い粒が星座のようにあって、その横に正三角形と棒グラフのようなかたちがあり、端のほうには途中でちぎれてずれた白い縦線が見えます。何かの写真ではあるのでしょうがまるでミロやクレーの絵画を見ているようで、天地左右 も定かではありません。しばらくその葉書を縦横に回転させて、やっとこれは、どこかの台所の一画を撮った写真らしいことが認識できました。星座のように見えたのは台所の壁にかかったフライパンや壷などであり、左端にの白い線は樋でした。そして右端には鍋がのったレンジ台のようなものも写っています。しかしフライパンや鍋の横にある三角や棒グラフのようなものは何なのか依然不明です。それにしてもなにか現実感がなく、かなりシュールな感じがして、また、こんなものをなんで絵葉書にしたのか不思議に思い、興味が引かれました。よくわからないまま300円でその葉書を買って家路につきました。帰宅後、ゆっくりその葉書の裏面のキャプションを判読したところ、この絵葉書の写真は、「ポンペイ遺跡のFullonicaの台所」であるということが判明しました。これで納得です。古代ポンペイの人たちの生活が1700年前のベズビオ火山の噴火により閉じ込められ、記録され、それがまた20世紀になって開発された写真機によって記録され、その写真が撮られたあとにまた何十年かの時間が経過することによって生ずる時の堆積。それが私にこのシュールな感覚を抱かせたのだと思うのです。この一枚の絵葉書から、「記録性」ということの面白さにあらためて気づかされたように思いました。 (六田知弘)
- 2006.04.12 傍らの信楽の壷
-
私の傍らにひとつの信楽の壷があります。それを眺めているといつも言葉は遠くに消え去ります。中世の秋の野山にひとり分け入り、遠く近くの景色をただ無言で眺めているときのように。 (六田知弘)
- 2006.04.05 高幡不動の桜

いつも通っている高幡不動の裏山の桜も満開です。 枝いっぱいに花がたわわに咲き誇るりっぱな木もいいのですが、金剛寺の日月山水図屏風の桜ように、山の斜面にほかの木々に混じって花咲くさくらも大好きです。 (六田知弘)
- 2006.03.29 ロマネスクの怪物たち
-


ヨーロッパにおいて、10世紀後半から12世紀初頭にかけて数多くのロマネスク様式の建築物が建てられました。後の天を突き刺すような尖塔を持つある意味で神経質にも思えるゴシック様式とは異なり、ロマネスク様式の教会堂はまるで大地の一部が聖なる力で盛り上がってできたような、簡素で重厚な姿です。そして、内陣に一歩踏み入れると、そこにはゴシックやバロックの教会堂よりもずっと世俗をはなれた聖なる空気とひかりに満たされていることに私たちは気づきます。
ロマネスクの教会や修道院の建築の外壁や扉口、内陣や回廊の柱頭にはさまざまな彫刻がそして内陣の壁面にはきわめて個性的なフレスコ画を見ることができます。
それらのテーマは旧約や新約聖書の物語であったり、聖人たちの姿であったりキリスト教の教義に関係するものが多いのですが、その一方でキリスト教とは一見無関係に思われる一般民衆の生活場面などの図像とともに不思議な動物や空想上の生き物すなわち怪物の姿、そして幻想的で怪奇な悪魔の姿がしばしば見受けられます。
後のゴシックにもガルグイユ(怪獣の姿をした雨樋)などに怪物の姿が現されていますがそれらは確立されたキリスト教会の権威のもとで様式化され教会の装飾の一部になりさがっているように思えます。しかしロマネスクのものは、同じく建築の一部分であるのにもかかわらず、それぞれの怪物たちや悪魔たちは今もいのちを保ち、教会堂に佇むわれわれはどこからかその生暖かい息遣いを感じとります。
旧約聖書の福音書家の象徴である体が人で頭だけが獅子や牛や鷲のほかにも、頭と翼は鷲で体は獅子のグリフス、頭は獅子で体は山羊、尾は蛇で火を吐くキメラ、有翼あるいは無翼の竜、半人半馬のケンタウロス、美女の顔を持ち体は鳥のセーレーンやハルピ、二つの尾をもつ人魚、犬頭人身のキノケファルス、背丈の半分もありそうな巨大な耳を持つ者や、梯子を使って馬に乗る小人、翼を持った虎、頭がひとつで体が二つのひげ男、魚の胴体でキリギリスのような長い後ろ足をもつもの、有翼のいたち、全身が長い毛に覆われた人獣、人を頭から食らう頭だけの獅子、そのほか現実の世界にいそうでいないふしぎなすがたの動物たち。数え切れないぐらいの多種多様の怪獣たち。そして最後の審判で地獄に堕ちた者をいじめぬく有翼の悪魔たち。これらのバケモノたちはみなロマネスクの宇宙のなかで時をこえて今も生き生きと跳梁跋扈しているのです。わたしは、子供のころからおばけや暗闇が怖くて一人で夜トイレにも行けなかったほどなのですが、何故だか怪物にはつよく惹かれるところがありました。四天王に踏みつけられて顔をゆがめる三本指の餓鬼の姿や極楽で鳴くという人頭鳥身の迦稜頻伽や共命鳥、そしてかっこいい龍の姿にいまだにこころがさわぎます。
ところでこれらのロマネスクの怪物たちは中世のその時代に生きた人たちにとって何を意味したのでしょうか。かれらは、これらの彫刻や絵画を見て何を感じていたのでしょうか。そしてなぜこれらか聖なる教会堂や修道院に彫刻され、描かれているのでしょうか。
安部謹也氏はこれらの怪物たちをキリスト教が入る以前のヨーロッパ世界で信じられていた土着の信仰のうちにあって一般庶民が恐れ敬った、自然という大宇宙に棲み、それを支配すると信じた神々や怪物のすがたであるとし、未知の大宇宙に本当にこれらの怪物たちが棲んでいると信じ、怖れた農民や市民に対し、キリスト教会は教会の玄関上部の壁や入口にこのような怪物たちの像を配置することで、それらがキリスト教会のなかに組み込まれていることを示したのだと言います。
確かにそういうことがいえるように思います。そして12世紀半ばごろからゴシックに入り、キリスト教会の教義が庶民にいきわたるようになってから怪物たちはすっかり生気をなくし、ガルグイユのような窮屈なかっこうで鎖につながれて辛うじて生き延びるしかなくなるのです。そして教会堂における怪物の数も急激に減っていきます。私はこのとき、ヨーロッパ世界では大きな転換点を迎えたのだと思います。すなわち人間と自然との関係が大きく変わった。つまり、自然の一部としての人間が、自然に対峙する存在に変わったのだと思うのです。もちろん、これは、キリスト教会のなかだけでいえることで、庶民の生活のうちでは依然として自然を怖れ、怪物を見ることもあったでしょうが。
長くなったので中途ですが、このへんでやめようと思いますが、いずれにせよロマネスクの空間に立つとき、そこに息づく怪物などの姿を通して、われわれが忘れかけている自然の一部としての存在であった人間の心性がひしひしと触覚的に伝わってくるのを感じるのです。わたしはロマネスクのそんな部分に強く惹かれるのです。 (六田知弘) - 2006.03.23 写真に写されたもの
-
先週のこの欄にも書きましたように3月22日から4月8日まで写真展「POLI」を開 催します.先日、その会場設営をしたのですが、壁面に並んだ写真を見て、10年以 上も前に撮影したものなのに不思議とそれら一枚一枚の写真を撮ったときのその瞬間 を思い出しました.といっても具体的な状況というよりカメラを設置し、シャッター を切るまでのほんの1~2分、ながくても10分という刹那の自分の心的状況という か、そのとき五感で感じた心的時間というようなものがフッとよみがえってくるのを 感じたのです.写真は外界を物理的に写し撮る機能と同時に、それを望む望まぬにか かわらず、写した人間の精神あるいは心的状況も記録する不思議な機能も備えている ようです.だからこそわれわれは写真というものに魅力を感じるのだろうと思うので す.ですから私は自分の心的状況を表現するために特殊なテクニックなど使う必要は ないと考えます.そんなことをしなくてもそのときの自分の姿はそこにいやおうな く、しっかりと刻印されてしまっているのですから。ということは、自分が撮った写 真をひとに見てもらうということは、ある意味で非常におそろしい行為であるとも言 えるのですが。(六田知弘)
- 2006.03.15 写真展「POLI」
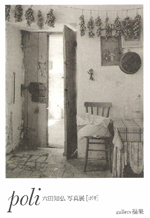
11年前、私はイタリアのポリという村でひと夏を過ごしました。もちろん撮影の目的でです。ポリはローマから約30キロ東南東に位置し、中世山岳都市の面影を色濃く残していて遠くから眺めるとまるで天空の城砦都市のように見えます。私は、その村のはしっこにある小さな離れのような建物を借りてそこでひとり寝起きをしたのです。その部屋に持ち主のおばさんに案内されて一歩入った瞬間、私はすっかり気に入りました。とても気持ちいい空気と光が部屋に充満していたからです。窓の外は、いきなり谷間で、その対面の急な斜面にはちいさな畑と馬の姿が見えます。ますます気に入りました。そしてその夜、その部屋がさらに魅力的に思えるようになることがありました。といいますのは、シャワーを浴びようと浴室に行ってふとバスタブを覗いたらなんとそこにサソリがいるではありませんか!ちいさいけれどそれは紛れもなくほんものの生きたサソリです。わたしは嬉しくなり、急いで服を着直して棒切れを箸代わりにサソリをはさんでワインの空き瓶に慎重に入れました。こいつを飼ってやろうと考えたのです。それを暖炉のうえに置いて改めてシャワーを浴び、そしてサソリを一頻りながめた後、電灯を消してキュウキュウと軋むベッドに横たわりました。暑いので枕元の窓を開けたままでした。そしてウトウトとしたころ、私のこころをときめかす次の訪問者が現れたのです。頭の後ろからいきなり部屋に飛び込んできて私の頭上を飛び回る黒い影。その影は数秒のあいだ私の部屋の空気をかすかに揺るがしたかと思うと目も留まらぬ速さで窓から出て行きました。暗くて、そして早すぎてよく確認はできなかったのですが、あの影はコウモリに違いありません。なんとすばらしいところに来たものかと私はここちよい気持ちで眠りに就きました。 そんな「POLI」で撮った写真を3月22日から4月8日まで東京神田神保町のgallery福果で展示します。(地下鉄神保町駅A7出口を出てすぐ「さぼうる」隣「六法」の2階 /TEL03-3959-6555 /12時-19時 /日曜休廊) 写真集「ポリの肖像」に今回展示の作品がすべて載っておりますが、新たにつくった自信のモノクロプリントを是非ご覧いただければと思います。お待ちいたしております。(六田知弘)
- 2006.03.08 ニューヨーク・バークコレクション展
-
東京上野の東京都美術館で開催されていた「ニューヨーク・バークコレクション展」 に行ってきました。ハッキリ言ってショックをうけました。これが全てアメリカに いってしまったのだと考えると・・・。バークコレクションはアメリカ ミネソタ州 出身のメアリ-・バークという女性が蒐集した日本美術の大コレクションです。「日 本の美 三千年の輝き」というサブタイトルが示すように縄文中期の土器から江戸期 のものまで、日本美術を系統だってあつめていますが、数的にいっても質的な面からいっ ても絵画がもっとも充実しています。それにしてもこのレベルの高さはなんなので しょう。戦後、日本人のお金持ちが海外の美術品や日本の民芸的古美術品の蒐集に力 を注いでいる間にこれほどまでの質と量の日本の美術品が海外のコレクターのもとに 渡っていったのだと思うと情けないというかなんと言うか・・・。しかし逆に考えれ ば日本の美術のレベルをそして日本人の世界観を海外に知らしめるという意味では非 常に意味のあるコレクションだと言えるのですが。
ところで、この展覧会を見て強烈に感じたことなのですが、なんと日本の美術は特異 なデザイン性を有していることか。鎌倉期の春日宮曼陀羅から桃山の柳橋水車図屏 風、そして江戸後期の若冲の月下白梅図に至るまでその時空を超えた異次元のリアリ ティーをつくり出すデザイン性。それは単なる装飾という次元を遥かに超越して、見 るものに「宇宙」なるものを感じさせるのです。こんな美術は世界中さがしてもそう あるものではないとあらためて思いました。(六田知弘) - 2006.03.01 高幡不動の裏山の松の木

前日の雨もあがり、ほんの少し春めいた昼過ぎ、いつものように高幡不動の裏山を 通って駅まで行きました。ひょろっと高い松の木が数本、その黒い影でみずいろの空 と白い雲を区切っていました。「まだある。」とにそこを通るときいつも思います。 夕暮れどきにこの道を通るときには、松の木越しに左側から右側へきれいなグラデー ションで暗くなっていく空を眺めて、地球の自転とその地球の上に立っているあまり にもたよりない「私」という存在の位置を測ります。しかしここ一、二年でこの裏山 の木も墓地の造成などでずいぶん伐られてしまいました。
木といえば中学1年生の私の息子にも特別な木があります。それは彼が呼ぶところの 「秘密の木」です。「秘密の木」は息子が通っていた幼稚園の近くのちいさな林にあ る一本のクヌギの老木です。9年前の夏にそこでりっぱなノコギリクワガタを採って から毎年コクワガタやスジクワガタ、カブトムシなどが採れ、また、自宅で孵化させ たカブトムシをその木に放したりして虫好きの父子にとっては誰にも教えたくない一 本の大切な木なのです。ところがここ数年でその存亡が危うくなってきたのです。少 しずつまわりのコナラの木が伐採され、その魔の手がどんどん「秘密の木」に迫って くるのです。息子が言うには去年の夏にはその木一本だけ奇跡的に残されていたとい うことです。
時の流れの中で全てのものは移り変わります。それはどうしようもないことなので しょうけど、たかが一本の木されど特別な木というものもあるのです。(六田知弘)- 2006.02.22 「大いなる遺産 美の伝統展」
-
東京美術倶楽部で開催されている「大いなる遺産 美の伝統展」に行ってきました。
これは、東京美術倶楽部創立100周年を記念して美術商たちがかつて扱った古美 術、近代絵画、近代工芸を展示したもので、国宝十数点を含む逸品ぞろいの展覧会で す。国宝室には、私の大好きなあの青磁の下蕪瓶も東博にあるときとは違う種類の光 をうけて静かにならんでいました。頬擦りをしたくなるようなその形と釉調に長時間 見入ってしまいました。そのほかにも根津美術館の「鶉図」にも引き込まれました。
そして叶うことならいつかそれらをガラス越しではなく、そしてやわらかい自然光の もとで見てみたいと思いました。(六田知弘) - 2006.02.15 パウル・クレー
-
東京の大丸でのクレー展を見てきました。やはりクレーは私にとって20世紀最大の 画家なのです。クレーの絵を見ていると変な言い方ですが私の心の襞を指先で撫でつ けられているような、そんな触覚的な内的リアリティーを強く感じます。クレーは言 います。「芸術とは目に見えるものの再現ではなく 見えるようにすることである」 と。われわれにとって、ものをほんとうの意味で見るということ、ものの存在の本質 なるものを実在感あるものとして捉えるということ。それは極めて難しいことに思い ます。しかし、芸術はそのものの本質を捉え、そして内的作用を経たのちにそれを目 に見えるものとして別次元で表現する行為であるとクレーは言っているのだと思いま す。いったい、ものに本質というものがあるのかどうか私にはわかりませんが、彼の 作品は抽象的な一本の線であってもなんとリアリティがあるのでしょう。クレーの作 品を見ていると確かにものの本質のようなものを捉える眼をもった人間がその実体を も超越したものまでも見通し、そしてそれを内面で高い次元で昇華し、実在感あるも のとして新たなかたちでアウトプット=表現する能力を彼は獲得したのだと思うので す。まさに「内的リアリティ」なのです。写真をする者が自分のフィールドにちょっ と引き寄せ過ぎた見方をしてしまったかもしれませんが、やはりCGユング、ロバート ・フランクそしてこのパウル・クレーの3人のスイス人は私にとって特別な存在とい えるのです。(六田知弘)
- 2006.02.08 雪の積もった家並を見るていると
-
2月7日、夜半すぎ窓から外を眺めると一面の雪景色でした。
あたりの家々の屋根も真っ白に統一されて、まるでヨーロッパの町並みを遠くから眺めているようです。スペインやイタリア、フランスなどの田舎を車でまわっているとオリーブや葡萄の畑の向うに町が見えてきます。その町の建物は、町によって色や形にそれぞれひとつの統一感をもっていてとても美しく感じられます。日本のようにそれぞれの家が好き勝手な色や形で建てられているのではなく、昔から引き継がれたコミュニティーを単位とする美意識を持って町がデザインされ、形づくられていることがわかるのです。雪明かりに浮かび出る青白色に統一された住宅街の屋根の固まりを曇ったガラス越しに眺めていると儚い夢の続きを見ているような気分になりました。(六田知弘) - 2006.02.01 「空(うつろ)」となってものに向き合うこと
-
私は写真を撮るときに、できうる限りニュートラルな状態で被写体に対したいと考えます。自分のそのものに対する固定観念や既成観念をなくし、浅薄なイメージのフィルターを被せることなく、そして写真を見る人が望むであろうイメージをなぞることなく、今、ここにある、このものにただ「空(うつろ)」となって向き合うこと。それができたら最高です。先週書いたアジェやウォ-カー・エヴァンズやロバート・フランクはその数少ない先輩です。そのすばらしさと難しさをますます痛感しているこの頃です。(六田知弘)
- 2006.01.25 ロバート・フランクの「THE AMERICANS」のプリント
-
先日、ロバート・フランクの「THE AMERICANS」の中の一枚のオリジナルプリントをその所蔵者の方に見せていただく機会を得ました。
シートをかぶせられた車の側面が前面にあり、車の背後には二本のヤシの木とその影が映ったコンクリートの塀がある写真です。そういうとどの写真かすぐに思い浮かべられる方もいらっしゃるかと思います。このロバート・フランクの「THE AMERICANS」は1955、1956年に撮影されたものですが、ウイリアム・クラインの「NEW YORK」とともにその後の世界の写真シーンに極めて大きな影響を与えた写真集です。私にとってもこのロバート・フランクの「THE AMERICANS」はユジェーヌ・アジェ、ウオーカー・エヴァンス、土門拳、東松照明らの作品などとともに非常に大きな影響をうけたもののひとつで、学生のころちょうど復刻されたこの写真集を購入し、汲んでも汲んでも汲みきれない大きな井戸の水を小さな釣瓶で汲み上げるように繰り返し、繰り返しページを繰ったことを思い出します。そして写真というものがもつ魅力にぐいぐいと引き込まれていきました。あれから30年近くたった今、そのロバート・フランクのプリントを見て、思ったこと。それはちょっというのは気恥ずかしいのですが、自分が写真でやろうとしていることは、やはり間違っていないのだというある種の確信のようなものでした。(六田知弘) - 2006.01.18 ゴーギャンの「赤」
-
先日、岡山に用があったついでに倉敷の大原美術館に立ち寄りました。
そこで、二十数年ぶりにあのゴーギャンの「かぐわしき大地」をじっくり見る機会を得ました。この絵はゴーギャンのなかでも特に好きなもののひとつです。やはりタヒチで描かれたもので、熱帯の植物のなかに褐色のたくましいマオリの娘の裸体の立ち姿が足の先から頭の先まで画面いっぱいに描かれています。娘は体をほぼ正面に向けていますが、重心をすこし右側にかけるようにしながら大きな足で大地に立っています。そして地面からひょろっと伸びた不思議な花の先を右手でつまみ、左手は胸の下にかざしています。娘の背景にはゴムの木らしき一本の太い樹木がまるでこの娘の化身のようにどっしりと赤土の上に立っています。そして、その娘とゴムの木との間になんとも訳の分からない「赤」が描かれているのです。この「赤」がはじめてこの絵を見た私に強烈な印象を与えたことを今回、久しぶりにこの絵の前に立って鮮やかに思い出したのです.トカゲの黒いかげの上にその「赤」があるのでトビトカゲの翼のようにも見えるけれどもよくわからない形の深紅の陰影のない一つの平面が画面中央上部に描かれ、その尖った一端が娘の右こめかみに突き刺さっているようにも見えるのです.この鮮烈な「赤」はいったい何を意味するものなのでしょうか。私は、以前考えたひとつの仮の解答を確かめるつもりで遠くから、近くからこの絵を眺めました。そして導きだした今の私なりの答え、それは、「宇宙エネルギーの表出」というものです。このゴーギャンの「赤」は(以前私が考えたことと同じく)大地から現出した「マナ=霊」であるとともに有機物、無機物を問わず万物を生み出した宇宙の根源的エネルギーが、ゴーギャンのキャンバスににじみ出たもの。ゴーギャンはタヒチに行って強烈なマナの存在を感じ取り、それをキャンバスに自覚しながら描き込んだ。それと同時により根源的な宇宙エネルギーのようなものを感知していて、この絵のなかにそれを半ば無意識的に深紅の絵の具で描いていた。そういうふうに今の私には思えるのです。もちろんこの私の結論には何の根拠もないのですが・・・。(六田知弘) - 2006.01.11 ロマネスクの魅力
-
今年最初の「今週のトピックス」です。みなさん、今年も思い出したときにでもこのHPにアクセスしていただければうれしいです。 今年の正月は私は奈良に帰省し4日に東京に帰ってきました。そのあと昨年撮影したロマネスクの写真を整理しています。早くまとめて皆さんにご覧いただきたい。はやる気持ちをおさえています。
それにしてもどうしてロマネスクはこんなに私の心をひきつけ続けるのでしょうか? 同じヨーロッパの中世でもそのあとのゴシックだとそれほどでもないのに・・・。整理中の写真を見ながら撮影のときを思いだします。深い陰影のなかにものを浮かび上がらせる光、あたりに微かに漂う灯明のほの酸っぱい匂い、そして土の匂い。ほのかに暖かみのある列柱や壁石の触感、草木が風にそよぐ音、小鳥のさえずり、遠くから聞こえるグレゴリオ聖歌・・・。ロマネスクの空間に立つとき、五感全体、いやもしかしたら第六感といわれるものにまでもに非常に濃密に何かが働きかけてくるのを感じます。おそらくこの空間はキリスト教の、所謂「神」を観じさせるために人為的に演出された一つの装置であるといえるでしょう。しかし、たとえそうであってもその空間は、われわれが失いかけた、しかし、ちょっと大げさかも知れませんが、われわれ人類が生きのびていくうえで必要不可欠な何かを呼び戻してくれるものがあるように私には感じられるのです。(六田知弘)