トピックス
写真家・六田知弘の近況 2005
展覧会や出版物、イベントの告知や六田知弘の近況報告を随時掲載していきます(毎週水曜日更新)。
過去のアーカイブ
- 2005.12.21 横須賀浄楽寺の不動明王像と毘沙門天像
-
先日、神奈川県横須賀市にある浄楽寺の不動明王像と毘沙門天像の撮影をしました。
今年の8月3日付けの今週のトピックス「2005.08.03 運慶作、阿弥陀三尊と不動明王像」でとりあげたあの運慶作の木像です。はじめて見たときからこの二つの像、特に不動明王像には強くひきつけられ、いつかは撮りたいと願っていましたが、今回、来年の春に出版予定の私の英文版写真集に是非掲載させてもらいたいと浄楽寺さんにお願いしたところ、幸いにもご許可をいただき撮影できたというわけです。制作は両像とも文治5年(1189)と考えられ、天才運慶の青年期の代表作といえるでしょう。今、天才と書きましたが、確かに彼の技術的レヴェルの高さ、造形感覚のすばらしさは驚嘆すべきものがあります。しかし、それ以上に、彫刻に生きた豊かな生命を吹き込むという意味においてほかに例を見ないものをもっているように思うのです。言い換えればものに命をあたえるその源としての彼の人間性、精神性において私は運慶というひとりの人間の存在に敬服してしまうのです。それにしてもなんと温かみのある、親しみのもてるお不動さんでしょう。眉間にしわをよせ、右目をカッと見開いて左目を半眼に、口を歪ましその端から大きな牙をのぞかせる。怖いはずの不動の形相なのに、その頬や胸や腕なんかをふざけてツンツンとつついてみたくなるような。運慶作あるいは運慶が監修、監督して作られたといわれるものは他にも奈良円成寺の大日如来座像、韮山の願成就院の不動・二童子像、高野山金剛峯寺の諸像、東大寺南大門の金剛力士像、そして興福寺北円堂の世親・無着像などいくつか知られていますが、どれもそれぞれ魅力あるもので、そのなかにはやはり運慶という鎌倉時代に生きた一人の人間のたしかな魂の実在を感じるのです。いつか運慶の彫刻を私のカメラで網羅して「人間運慶」なるものを浮かび上がらせる。そんな企画を実現させてみたいとものだと夢をふくらませるばかりです。(六田知弘) - 2005.12.14 玉の蝉
-
先日、中国の玉の蝉を手に入れました。おそらく前漢のものだと思われます。
玉の蝉というと普通思い浮かべるのはアブラゼミのように大きく平たいものですが、そいつは4cmほどのニイニイゼミのようなかわいいいやつです。以前から玉蝉は探していたのですが、なかなか数が少なく、また気に入ったもの、そして私が買えるような値段のものがなかったのですが、今回やっと巡り合えたという感じです。自分が持っているものについてあまりひとにお話するべきではないとは思いますが、半分白化した半透明で薄緑色の玉質の味わい、そしてなにより平面と曲面の組み合わせによって構成された究極といっていいほどに洗練されたその形状。古代中国ではセミは土から生まれ出るということで「再生」を意味すると言われていますが、この玉蝉を見ているとあのまだ色づかない鑞細工のような、いま羽化したばかりのセミのすがたを見ているように思えてくるのです。(六田知弘) - 2005.12.07 龍門石窟の撮影で
-
中国に行ってきました。
去年8月から1年3ヶ月ぶりです。今回は洛陽近郊の龍門石窟の撮影でした。龍門は3回目ですが、今回は特に彫刻の細部に焦点をあてて撮影することにしました。そこで、あらためて愕然としたことがあります。彫刻の顔で良い状態で残っているもの、いいかえれば写真にたえられる状態で残っているのは全体の1パーセントにも満たないのではないか。ということです。私が見たのは一般のものが見ることができる範囲からだけなので堂内に入ってかくれたところには良い状態のものもいくらかはあるかも知れませんが、それにしてもさびしいかぎりでした。
私もふくめて一般人は龍門を訪れたらまず北魏時代の賓陽洞や唐代の奉先寺などの巨大な仏像に目がいき、それに圧倒されて小さな窟の細部にはほとんど目がいかないためにあまり気づかないものですが、細部はさんたんたるものです。その原因として考えられるのはまず自然の風化があるでしょう。そしてそれに加えて人為的要因、つまり廃仏棄毀釈や文革期の破壊、そしてなにより売買目的の盗掘があると思います。北魏時代の古陽洞などは龕のなかの交脚菩薩像全体がきれいに剥ぎ取られ、そのかたちが壁面に墨で塗ったかのようにくっきりとみえ、ここまでくると岩面から剥ぎ取る技術の巧みさに逆に感心させられてしまうほどです。いずれこの世に存在するものは仏像であろうとなんであろうといつかは消滅するものではあるのでしょうが、やはりあるべき空間にそのものがないというのは写真を撮るものにはさみしいものではあるのです。(六田知弘) - 2005.11.23 中国古代の暮らしと夢

いま、東京町田市立博物館で「陶器が語る来世の理想郷 中国古代の暮らしと夢-建築・人・動物」という展覧会を開催しています。
この展覧会は、建築家の茂木計一郎氏所蔵の建築明器と俑を核に構成されたものです。こうした古代において亡くなった人が来世でも現世と同じように生活が続けられるようにとの願いをこめて墳墓に副葬された明器、特に建築物やひとの生活の様子を形どったものをこれほど一同に集められたのははじめてと思われ、とても興味深いものです。わたしはそのポスターと図録の表紙の写真を担当させてもらいました。人家のトイレの真下に直結して設置された豚小屋、釣瓶と滑車のついた井戸、厩舎、鶏小屋、倉や望楼、厠、祀堂、そしていまでも北京の胡同にそのままの姿で残る四合院と呼ばれる四角い庭を囲んで建てられた住居などの建築物、そしてその建物のなかにあった竈、ひきうす、蝉を並べてのせたしちりんのような炉、脱殼機、薬研、酒器や匙や碗などの食器、寝台、たんす、椅子やテーブルなど。そして農作業の合間に蓑やザルや壷、あかちゃんなどを抱いてたのしげに踊る農民達、牛や豚を大きな包丁を手に持ち解体しようとする人、楽器を演奏する人達、まな板の上の魚をさばこうとする人、足で杵を踏み脱穀をする若い二人、肘をたてて頭を支え俗世のことなどなに知らぬ顔で寝そべる仙人のような男、尻を下ろしておおきな口をあけて笑う人、そしその周りにいた犬や牛、鶏、羊などの動物たち。そしてなんとそれら種々の明器を販売していた明器屋の店鋪まで。考えただけでもおもしろいじゃありませんか。こんな現世の生活をあの世までもっていこうと思った古代の中国の人々の人生はもしかしたら現代のわれわれのものよりももっと楽しいものだったのかも知れないとふと思ってしまうようなものたちです。工芸的、美術的にみて非常に高度な技術で作られた中国の名品を見るのもいいですが、こんな楽しい、そのときに生きていたひとたちのぬくもりが伝わるようなものに接するのもいいものです。中国のふところの深さはおそれいりました。
町田市立博物館での展示は来年1月15日まででその後、愛知県立陶磁資料館、細見美術館、岡山市立オリエント美術館、山口県立萩美術館・浦上記念館とまわり、最後に再び東京に戻って10月7日から12月10日まで大倉集古館で開催されます。ぜひ気軽な気持ちで見に行かれるとよろしいかと思います。
ところで、私は今月25日から12月2日まで中国に行きます。龍門石窟の撮影です。ですからまた来週のこの今週のトピックスはお休みさせていただくことになります。度々の休みですみません。龍門石窟の撮影についてはまた帰ってきましたらご報告いたします。(六田知弘)- 2005.11.16 感謝
-
朝晩がめっきり冷え込むようになり、今年も残り少なくなったということに気付きました。これまではそんなことがなかったので私も少し歳をとったのかも知れません。
先日、私が大学を卒業してから1年間アシスタントとしてお世話になった中村保さんを偲ぶ会に行きました。中村さんは今年10月に亡くなられました。中村さんには、駆け出しの私がなまいきにも写真に対する考え方で内心、反発することも多かったのですが、反発しながらも今から考えると随分教わったことが多く、また知らないうちに大きな影響をうけていたことに驚きます。私がネパールやイタリアを撮ることになったのも中村さんの写真に接してからですから。それとわたしの写真に関してほんとうにお世話になり、影響をうけたもうひと方、吉田元さんが4月に亡くなられました。吉田さんには私の写真集「ひかりの素足-シェルパ」そして「ポリの肖像」の構成に長期間お手を煩わせました。吉田さんの写真に対する鋭い思考と深い愛情には敬服するのみでした。吉田元さんの遺灰は先月、吉田さんの遺言どおり沖縄の黒島近くの海原にまかれました。中村保さんは彼が何十回も通ったネパールの地に散灰されるそうです。良きにしろ、悪しきにしろ今の私を形づくっているのは、何らかの縁でわたしにつながりを持っていただいたこれらの人々との出会いだと考えるとただ「感謝」です。(六田知弘) - 2005.11.10 ヴィック、教会の男
-
11月7日夕方、なんとか無事に帰ってきました。
フランスのテレビでも暴動のことを報道していましたが、私の行ったところは最終地のパリをふくめなんらきな臭い感じはなく、帰国してからテレビや新聞を見てそれが各地に飛び火して拡大し、夜間外出禁止令までだされる事態になっていることを知ったという具合です。ということで、今回のフランスにおける暴動は、私の撮影旅行にはなんら影響はありませんでした。というかロマネスク美術というような今の現実社会とかけ離れたものを呑気に追っていたから私には感じられなかったということなのかも知れません。
さて、何を書こうか、いろいろあって難しいところなのですが、今回まわったロマネスクの教会や修道院のなかで個人的にもっとも好きだったところから書くことにします。それは、フランス中部ロワール川流域の南東、べリー地方と呼ばれる地域にあるヴィックという十軒程度のほんとうに小さなの集落の小さな教会です。私がその教会に着いたのは、周りはじめてから3日目の夕方でした。外観はゴッホが描いたあのオーヴェールの教会となんとなく似ていて、とてもやわらかな落ち着いた佇まいをしています。わたしは、玄関のまえの空き地に車を停め、車窓から扉がわずかに開いているのを確かめてから、何も持たずに車を降り、見た目よりいくぶん重い分厚い木の扉を少し緊張しながら引き開けました。中はすでにかなり暗く、正面のアプシスと呼ばれる半球形の祭壇だけが一個の小さな灯明のひかりに照らされ、オレンジ色に浮かび上がっていました。誰もいません。私は鳥肌がたちました。翌日朝からカメラと三脚を持ってはいりました。堂内は、朝のひかりに満たされて壁面いっぱいに描かれたフレスコ画を隅々まで見せていました。わたしは夢中になって撮影しました。だれも来ません。いまこの空間はわたし一人のものだと思うと至福の時を感じます。午後4時、わたしがちょうど半球状のアプシスの正面に描かれたキリスト像の撮影をしていたとき、突然ギーという音とともに堂内がより明るくなりました。どうやら今日始めてのお祈りのひとが来たようです。わたしは、上方のキリスト像に向いたまま一枚シャッターをゆっくりと切ってから入口のほうをふりむきました。逆光でシルエットになった大きな人影が身廊の通路をちょっと片足を引きずるようにゆっくりとこちらに向かってくるところでした。そして、その影は私のいるアプシスの前のトランセプトとよばれる前室まで来て立ち止まり、そのとき私がそこにいることにはじめて気付いたようにちょっと驚いたように、そして怪しむようにわたしのことを鋭い目で睨み付けました。わたしはこれはマズイと思い、あわててボンジュールと言ってみたのですが相手は無言でますます強い眼でわたしを上方から睨み付けるだけです。その眼には殺気のようなものというか、狂気のようなというか、ちょっと尋常のものではないものがありました。私は極度の緊張状態のまま三脚に取り付けたカメラをかかえて彼の真ん前をすり抜け、もの音を一切たてないように出入り口近くの最後列の礼拝者用の長椅子にまでゆっくりと息を殺して歩き、そしてそこに腰掛けました。男は私が出ていったと思ったのか、そのあと外陣最前列の椅子のひとつに腰掛け、それから祭壇に向かってひざまずきゆっくりと十字をきりました。そして椅子に腰掛け、消え入るような小さな、低い声で5分間ほど祈りの言葉を発しているようでした。その後、ながいながい全くの沈黙が続いたのです。わたしは、もちろん身動きせずにその沈黙に同調せざるをえませんでした。というかその沈黙を楽しみました。聞こえてくるのは、堂内にいつの間にか入り込んだ花蜂のブーンブーンという羽音だけです。30分はその状態が続いたでしょうか。寝てしまったのじゃないかと思ったころ男の頭が少しだけ揺らいだかと思うと、男は一旦立ち上がり、それからひれ伏すというか、前方の床にに身をゆっくりと投げ出したようでした。そしてその状態でまた約5分。沈黙が続きました。その後男は、ゆっくりと立ち上がり、十字をきってただひとつの持ち物である布の袋を肩にかけてから祭壇に背を向けて私のいる出入り口に向かって、またゆっくりと左足をひきずりながら歩いてきました。こんどは、逆光ではないので私のほうからは、彼の姿ははっきりと見ることが出来ました。年齢は50代後半でしょうか。無精髭を生やし、うすくなった髪はみだれ、灰白色のシャツやズボンや靴はシミだらけでボロボロです。そしてやはりその眼光は突き刺すように鋭いのです。出入り口まで彼が来たとき、私にまたはじめて気付いたかのように立ち止まり、しばらく椅子に座っている私を見下ろしたあと、やはり無言で扉を開けたまま出ていきました。
それから5日後、私は南仏特有のミストラルとよばれる風の吹くなかプロヴァンスのサン・レミの修道院の廻廊に立っていました。そこは、ご存じの方も多いと思いますが、ゴッホがアルルで耳を切った後入院していた精神病院のある修道院です。(いまでもこの修道院付属の病院は現役です。)ゴッホはこの病院の周辺で多くの絵を描きました。あの怖いような澄明性をもった絵です。私は、そのロマネスク様式の廻廊を回っていたとき、なぜが、ヴィックの教会で会ったあの男のことを思い出しました。そして単純かもしれませんがゴッホとあの男とを無意識の内に重ねてイメージしている自分に気付きました。人にとって神とはなんなのか、そして祈りの空間である教会とはなんなのか。そんな解けるはずのない疑問を持ちながら撮影旅行を続けました。(六田知弘)


- 2005.10.20 ロマネスク美術の撮影へ
-
トピックス、二週分休ませていただきましたが再開いたします。
しかし、実はまた来週から二週お休みとなってしまいます。といいますのは、10月22日から11月7日までの予定でフランスのロマネスク美術の撮影旅行に行くためです。
以前からフランスやスペイン、イタリアなどのロマネスク美術を撮ってきましたが、そろそろ来年にはそれをまとめて発表したいと考えています。いままでは、教会や修道院の彫刻や壁画の撮影が中心でしたが、今回は建築空間に焦点をあててみるつもりです。まずは、パリの南西約250キロにあるトゥ-ルでレンタカーを借りて、ポアティエ、ショービニ-、サン・サヴァン、ノアン・ヴィック、オルシヴァルと南西へと向かい、その間数カ所に立ち寄りながら南フランスのプロヴァンス地方のシト-派の修道院を訪ねる予定です。帰ってきましたらまたこの欄で報告させていただきます。久々のひとりでの海外での撮影です。気を引き締めてよい仕事をしてこようと思います。来年はみなさまにそれらの写真をご覧いただけるようにするつもりです。乞う御期待。(六田知弘) - 2005.09.30 2週間お休み
-
トピックスの更新を2週間お休みさせていただきます。再開は10月19日(水)からとなります。(サイト管理:インプレオ)
- 2005.09.28 古墳時代の勾玉
-
前回は中国の玉について書きましたが、今回は古墳時代の勾玉です。大きな翡翠製のものが1個と標準的なもの2個、そして瑪瑙製のもの2個を撮影しました。勾玉を見るとその石の色や艶はもちろん、いつもその独特のかたちのに興味がそそられます。
私は、子供の時には勾玉というと人の霊魂を表わしているのだと思い込んでいたところがあります。おそらくそのかたちが人魂に似ていると思ったからでしょう。しかし、中学生のころに知識がついてくると、霊魂というより胎児をイメージしたものだと思うようになりました。一般的にはそのかたちは縄文時代、熊などのけものの牙に穴をあけてそれに紐を通してで首に懸けた牙玉から発達していったものだ考えられているようです。いずれにしろ勾玉は古代日本人の生命に対する思いが形象化したものではないかと、手の中でいじっていると思うのです。もちろんな何の根拠もないのですが・・・。(六田知弘) - 2005.09.21 中国の玉
-
このところ私は中国の「玉」を持ち歩いています。たけのこの形をしていて、そこにちいさな二匹の蝙蝠が彫り加えられています。大きさは8センチほどで、全体の形としては大きな書道用の筆の筆先をイメージしていただければよいと思います。2年前の8月に仕事で北京に行ったとき山のように「玉」あるいは練り物の玉様のものが並べられた露天市で見つけてきたものです。白濁した緑青で、その玉質と作行から清朝のものといってよいと玉に強い複数の古美術商のかたに言われました。この玉を掌にのせ握っていると、その形と触感から私はなにかある種のエネルギーを感じるように思えます。ストーンパワーとでもいうものでしょうか。実は私はこの石を買って帰ったすぐのころ、これをさわっていて3日間、ひどい熱が出でて苦しんだことがあります。もしかしたらこの玉のパワーにあてられてしまったのかもしれません。
谷崎潤一郎は『陰翳礼讃』のなかで「玉」にふれ、「あの、妙に薄濁りのした、幾百年もの古い空気が一つに凝結したような、奥の奥の方までどろんとした鈍い光を含む石のかたまりに魅力を感ずるのは、われわれ東洋人だけではないだろうか。」「しかしあのどんよりとした肌を見ると、いかにも支那の石らしい気がし、長い過去を持つ支那文明の滓があの厚みのある濁りの中に堆積しているように思われ、支那人がああ云う色沢や物質を嗜好するに不思議はないと云うことだけは、頷ける。」と「玉」の魅力とそれに惹かれる東洋人の美意識について「陰翳」というキーワードをもとにこの上もなく適切にその美の本質についてのべています。
たしかに私も「玉」がもつこの独特の美的な魅力につよくひきつけられます。そしてそれと同時にそれがもつパワーにも反応します。今こうしてこの筍形の玉を握っていると、内に満ちた生命エネルギーを意味する「筍」と、「福」を意味する「蝙蝠」とを組みあわせたこのかたちに、私は古の中国に地に生き、願いをこめてこの玉を握りしめていた人が実際に存在したことを実感として感じることができるのです。「玉」には何億年もかかってつくられた鉱物としての自然エネルギーとそこに手を加えた造作物としての人為的エネルギーとが合わさった、ある種宇宙的存在ともいえる「美のかたち」があるというふうに私には感じられるのです。(六田知弘) - 2005.09.14 アサギマダラ
-
9月のはじめのある日の昼すぎ、いつものように駅に行くため高幡不動の裏山をひとり下っているときでした。あたりはツクツクボオシの鳴き声に山中が満たされ、木漏れ日は先日までより微かに黄色見を帯びて山の路面を網の目のように照らし、緩やかな風にふかれて揺れていました。その光のなかを小さなトカゲが青いエナメルの尾をふりながら右から左へと走り抜けていきました。下から初老の夫婦らしい二人が登ってきました。わたしとすれ違う寸前に彼らのすぐ後ろを二羽の瑠璃色の小鳥がぴったりと寄り添い、羽を翻しながら光のなかを飛び抜けていきました。あの鳥はなんなんだろう。オオルリなのかコルリなのか。などと考えながらゆっくり下っていきました。かなり下って、お不動さんの鐘楼が見えかけたところでした。背後から一匹の大きな蝶がやって来てわたしの体を左から回り込み、足元の1メートル50cmはど前の地面に静かに降りたちました。アサギマダラです。この蝶をこの近辺で見るのははじめてで、以前、屋久島の縄文杉の前と故郷の葛城山の山頂で見てから何年ぶりかの出会いです。地面のわずかな水分を吸っているのか一分以上、羽を閉じたままそこに留まっていました。それからふわっと舞い上がり、私の前を一回転してから左脇のコナラの暗い林間を羽ばたきもせず夢のように空気に浮かんで抜けていきました。日常のなかに微かな非日常が漏れ出したような5分余りの小さなトリップでした。(六田知弘)
- 2005.09.07 青磁下蕪瓶
-

先々週に私の鑑賞陶器ベスト5を書きましたが、そのなかでも最も好きな陶磁器、つまり私にとってのベスト1は何かと考えたとき、アルカンシェール美術財団所有の「青磁下蕪瓶」(中国・南宋時代)か台北故宮博物院の汝官窯の舟形碗のどちらかが残るってくるように思います。
その二つのなかで強いて一つを選ぶとなるとやはり「青磁下蕪瓶」となるかも知れません。この「青磁下蕪瓶」は東京国立博物館の東洋館にわりとよく展示されていて、博物館を訪れるときにはこの焼物に会うのが私にとってずっと以前からの楽しみでもあります。鍔状にひらいた口から下に向けてわずかにひらきながら程よい太さで伸びる首、その下に蕪の様にというか、大きな柿の様にというか、鏡餅の様にというか、なんとも言えず充実した丸く柔らかく張った胴、そしてその下に広くやや高めの高台。全体の形、比率がこれ以上ないと思える程みごとなバランス。それに加えていわゆる粉青色のやや灰白味を帯びた青緑の抜群の釉色。そしてその肌のややマット味がかかりながら内からにじみ出るようなまさに玉(ぎょく)のような艶。変な表現ですが、思わず頬ずりをしてその温度と硬さを確かめてみたいという衝動にかられるような。私にとってはまさに究極の美のかたちと言っていいのかもしれません。この美を表現するには私の言葉など全く無力なものに思われるのです。
ところで、この「青磁下蕪瓶」は昔から名品といわれ、陶磁器では数少ない国宝に指定されているようなものなのですが、実はその制作された窯はまだ確定されてはいません。
20年ほど前の本には南宋官窯あるいは修内司官窯となっているものが多かった様ですが、最近ではほとんどの本で龍泉窯とされているようです。昔は、民窯の龍泉窯より官窯のほうが当然、作がよいはずという理由からこの「下蕪瓶」は南宋官窯だとされたようですが、最近では龍泉窯でもなかなか作振りの良い上手のものもあるとされ、そこに南宋官窯は黒い胎土でいわゆる紫口鉄足、二重貫入であるという昔からの原則が根拠として加わってこの「下蕪瓶」は官窯ではなく龍泉窯であるとされるようになったようです。(この下蕪瓶は釉薬が薄い箇所を良く見ればわかりますが、胎土は灰白色で貫入もありません)
ところが近年、幻の南宋官窯とされていた修内司官窯の窯跡が杭州の老虎洞で発見され、そこから出土する陶片が民間によってではありますが最近公表されたようです。それによるとそこから出土するものは、もうひとつの南宋官窯である郊壇下官窯のものと同じ黒っぽい胎土で二重貫入のあるものに混じって白、黄、灰白色の胎土で貫入のないものも少なからず発見されたといいます。
実は、先日わたしはまさにその老虎洞窯址から出たという数片の陶片を見る機会をえました。そのなかにこの「下蕪瓶」と釉色も胎土の色も肌の艶もそのカーブの具合もそっくりなものが一つ含まれていたのです。わたしはその陶片を掌にのせて指でその感触を確かめ、そして飽かずに眺めました。そしてこれは、龍泉窯ではないということにある確信を持ったのでした。私は陶磁器の研究者ではありません。それゆえ間違っている可能性も十分あります。しかしこんなふうに自分が惹かれる美なるものを眺めて、触れて、思いを巡らすことが私の大きな楽しみではあるのです。(六田知弘) - 2005.08.31 古面の撮影
-
古面の撮影をしました。乙とよばれる女面です。乙は、おかめ、お多福の原形といわれ、やや下膨れでほおが出て、おでこが前にせりだしています。鼻が丸く、目尻はさがり、いわゆる福々しい顔相です。
古面はいままでに何度か撮影したことがあります。そのときいつも思うのは光のあたり具合と見るアングルによってその表情が大きく変化するということです。それは、当たり前のことで能面などは、その傾けかたによって非常に微妙な心理、感情の変化を表現するものでしょうから。それにしても今回撮影した女面の変化のしようには驚きました。ファインダーを覗いていてすこし恐ろしくなりました。異なったライティングやアングルで数パターン撮影し、その写真を並べてみたところがどう見てもそれらが同一の面であるというふうには思えない程の違いでした。福々しい顔、妖艶な顔、無気味な顔、厳かな顔、エロチックな顔。どの写真を選べばいいものやら。そういえば尉や鬼神、霊男、翁などの男の面より女面のほうがはるかに変化が大きいように思えます。これはやはり実際の人間に関してみても男性よりも女性のほうがより多面な顔=精神性をもっているということの現れなのかもしれません。オソロシイ・・・。(六田知弘) - 2005.08.24 鑑賞陶器ベスト5
-
ちょっとマニアックかも知れませんがお赦しください。
日本陶磁協会発行の『陶説』8月号は「鑑賞陶器の百年」という特集をしています。そのなかで、研究者、古美術商、コレクター、陶芸家など50人を対象に「鑑賞陶器ベスト5」のアンケート調査の結果を発表していました。国の内外を問わず、日本製のものを除く陶磁器のなかで「これぞ名品」「私のすきなもの」を順位は関係なく5点選んで、その理由を答えたものです。これは、50人の回答者のなかに私の知人も多かったこともあり、とても興味深いものでした。結果は
1位 国宝・曜変天目(静嘉堂文庫美術館)
2位 重文・青磁輪花鉢<南宋官窯>(東京国立博物館)
3位 重文・白地黒掻落牡丹文瓶(永青文庫美術館)
同位 重文・三彩貼花文壷(静嘉堂文庫美術館)
・・・と続きます。わたしは、静嘉堂文庫美術館の曜変天目<=稲葉天目>が1位になったことに対して、『陶説』編集部の森さんと同様、ちょっとばかし意外でした。室町時代の美的価値観が現代でも変わらずにあることが・・・・。それでは私のベスト5は何かと考えたとき、アンケート回答者のみなさんも同様だったと思いますが、これはなかなか5点にしぼるのは容易ではありませんでした。強いて選ぶとすれば
●国宝・青磁下蕪瓶(アルカンシェール美術財団)
●国宝・曜変天目(藤田美術館)
●青磁舟形碗<汝官窯>(台北故宮博物院)
●重文・青磁九龍浄瓶<高麗時代>(大和文華館)
●重文・青花草花文面取瓶<朝鮮時代>(大阪市立東洋陶磁美術館)
でしょうか。ほかにいくつもいれたいものがあるのですが・・・。私は世界に3点ある曜変天目のなかでも藤田美術館のかそけきオーロラのような虹彩が、台北故宮の汝官窯のあの有名な水仙盤より内側からかすかに紅色が浮かび上がるしびれるような釉色の舟形の碗のほうが好みです。この『陶説』のアンケートは鑑賞陶器に関わる方々のそれぞれの美の価値基準を知ることともなって私にはとても参考になり興味深いものでした。(六田知弘) - 2005.08.17 夜の川遊び
-
夏休み、奈良県に住む母とおいと私の息子の4人で2泊3日で紀伊山地の山中へ行ってきました。
一泊目は和歌山県の本宮にある川湯温泉に泊まりました。川湯温泉はその名のとおり河原や川底から温湯が湧き出ている珍しい温泉です。とっぷりと日が落ちた8時すぎ、わたしは電燈のない川岸の、温泉と川水が混ざった熱くて冷たい複雑な水温の湯につかり、川原石を枕に夜空の星を仰いで寝転びます。息子とおいっこは夏の大三角形が見えるとかクツワムシが鳴いているとかいいながら真っ黒な川水に浸かってはじめての夜の川遊びを楽しみました。二泊目は奈良県側の十津川村の上葛川という山深いの集落の民宿に泊まり、アマゴが群れをなしておよぐガラスレンズのような信じられないくらい透明な渓流の淵で遊びました。日本にこんな場所がまだ残されていたこと、そして子供とともに久しぶりにピュアな自然を感じる時を過ごせたことに、誰に対してというわけでもなくただ自然に感謝のような気持ちがわいてきました。(六田知弘) - 2005.08.10 大徳寺大仙院の枯山水
-
八月の突き刺すような陽光もわずかに和らいだかと思える午後4時過ぎ、私は京都大徳寺の大仙院の縁側でひとり枯山水の庭をながめていました。
白い小砂利に波紋が描かれ、二つの円錐が長方形の庭の中心からかなり左にはずれたとこころに同じ白砂利でつくられています。そしてその波紋と円錐形の山に斜めから陽があたってその左側に濃い影をつくって驚くほど立体感を感じさせたかと思えばしばらく陰り、なんともフラットなとりとめのない感じになったりもします。そんな変化をしばらくながめていました。そこに一組の外国人のカップルがやってきて私から右へ数メートルはなれ たところに座りました。そのあとにも何人かの人がきてその縁側に座ったようでした。私は蝉時雨といつはじまったのか知れない隣の塔中から流れてくる読経の声、そして時折思いついたかのように啼くキジバトの声を聞きながら庭にあたる光の様子をぼんやりと眺めていました。
一時の非日常の白い時間が流れました。
そしてそろそろ帰ろうかと立ち上がってまわりを見たときわたしは少々驚かせれました。まわりにはいつのまにか十人をこえるひとたちが座っていたのですが、その人たちは全員西洋人だったのです。考えてみると彼らはこの縁側に座って誰もが無言で十数分間ただ庭を眺めていたということです。私は、ほんの一時ではあるのですが、遠くから来た彼らとこの日本におけるある意味で特殊な時空を知らないうちに共有していたのだと思うとすこしうれしくなりました。(六田知弘) - 2005.08.03 運慶作、阿弥陀三尊と不動明王像
-
先日、神奈川県横須賀市にある浄楽寺を訪ね、運慶作の阿弥陀三尊と不動明王像、毘沙門天像を見せていただきました。なかでも私は不動明王像には強く惹かれました。
玉眼がはいり、頬がふくらんだまんまるい顔に、筋肉隆々というよりどちらかというとぽちゃっとした肉づきの腕や足や胸元と、黒褐色で艶のあるその肌からうける印象は、たとえてみれば南海の島国から来た若き幕下力士といったところでしょうか。そしてこの像はわたしに京都の高山寺にある仔犬の彫刻を思い出させます。その30cm足らずのちょこんと座って首を少しかしげた愛くるしい仔犬の像は、以前は運慶作といわれていたのですが、近年、確か運慶と関係する別人の作とする説が有力だと聞きました。しかしそれにしてもこの二つの像に共通する表面的動きを抑えながらもその内面からあふれだす生命感の表出は、日本のほかの作者の作品にみつけることができるでしょうか。古今東西ほかの仏師には見い出すことかできない運慶独自の天才性を、それも孤高の天才というより我々の身近な生命を温もりをもってつかみ取り、それを新たなかたちで現出する、運慶というひとつの生きた個性の存在をふたつの像から強烈にを感じるのです。(六田知弘) - 2005.07.27 あるコレクターと
-
7月23日、午後4時すぎに千葉県沖を震源地とする比較的大きな地震がありましたが、東京都心部でもわりと揺れました。私はそのとき、ちょうど知り合いの美術品コレクターのお宅でそのコレクションを拝見していたところでした。その方は、そのコレクションのしかたが非常に変わっているというかそのやりかたのユニークさ、極端さで、知る人ぞ知るという存在です。まず、その量の膨大さにおいて、そしてその範囲の広さにおいて、そしてなによりそのコレクションの保管の仕方において。こう書くとよくいるがらくた蒐集家と思われがちですが、どっこいそれがひとつづつよく見ると、私がいうとなまいきに聞こえるかも知れませんが、それぞれ見どころがあるものばかりで感心させられ、非常にうらやましくも感じ、写真も撮りたくなりました。あまり詳しくここで書くのはひかえますが、とにかく私は床も壁面もその山のようなコレクションにうめ尽くされたひとつの部屋のなかにいるときにあの地震にあったのです。幸い震度は4程度でたいしたことはなかったのですが、それでも棚のものがいくつか落ちて、後で見るとほかの部屋にあった木製品のひとつが真ッ二つに割れていました。そこからの帰り、JRや地下鉄が運転見合わせをしていたため路線バスで最寄りの駅まで行き、ここまでは極端ではないにしろ子供のころから蒐集癖のある私を含め、ひとは、特に男性は、なぜモノを集めるのか、とりとめもなく考えながら列車の運転再開を待ちました。(六田知弘)
- 2005.07.20 サント・ドミンゴ・デ・シロス修道院の廻廊
-

ロマネスクのプリントを断続的に続けています。
作業をしながらあらためて感じたことというか確認したこと。それはやはり「祈りの空間」にはそこの光が非常に大きなポイントを占めるということです。西洋の教会に限らず、東洋の社寺やイスラムのモスクにおいても同じことが言えると思いますが、祈りの空間は日常の時空とは異なる「トポス」、つまり神を感じ、仏を観じる「場」なのですが、その特殊な空間を演出するのに光が極めて大きな役割をはたしていると思うのです。
私は今、ロマネスクの彫刻の写真をプリントしていますが、それらの彫刻は、それを彫るときからそれが置かれる空間と光の効果を計算にいれて彫刻されているように思われます。その顕著な例としてスペインのサント・ドミンゴ・デ・シロス修道院の廻廊の柱頭彫刻があります。廻廊の四角い中庭には光がふり注ぎ、その光が地面や床にあたって、柔らかい反射光が柱頭彫刻を下から照らしだします。そしてその光につつまれて柱頭の獅子やいたちや鷲やアルピなどの空想動物や聖人達がいのちを得て我々に囁きかけてくるのです。そしてその囁きを聞きながら廻廊をまわっていると天上の世界と自分とがつながりを持てたかのように思えてくるのです。光の重要性は、美術全集でそれらの彫刻を見た時と実際にその空間に立ったときとはその印象か大きく異なることでわかります。美術全集の写真はほとんどが人工のライトをあてて撮影します。それも博物館にある彫刻を撮影する時のように少し上方からのライティングです。これでは美術品としての彫刻としてはよくわかるものにはなりますが、魂にかかわる「祈りのかたち」を写したことにはなりません。わたしは、やはり自然光にこだわっていこうとあらためて今、思っています。(六田知弘) - 2005.07.13 ロマネスク美術
-

今、これまでに撮りためたロマネスク美術の写真のプリントをしています。
すでに200枚ほどはできたのですが、残りはまだまだ大量にあるのにすでにひどい肩こりで往生しています。しかしここで一気にやってしまわないといつまでたってもまとめることができません。
ところでロマネスクの美術は日本ではほとんどお目にかかることはできません。日本の博物館や美術館では現物を見ることはほとんど不可能です。それは、そのほとんどがヨーロッパの教会や修道院の建築あるいはその付属物であるからです。つまりロマネスクの美術は現地のその空間のなかに自ら足を踏み入れないと見れないものなのです。そんな当たり前のことにあらためて気づき、私が撮った写真にその光に満ちた空間にある独特の造形をしっかり写しとめることができているのかプリントをしながら確認しているというところです。
7月2日で神保町のギャラリー福果での私の写真展「ローマ・時の壁」は終わりましたが、第二会場の表参道のインプレオ・ギャラリーでの展示は7月16日(土曜)なで引き続き開催しております。お近くにいらっしゃったときには是非お立ち寄りください。福果においでいただいた方も、お時間があれば是非。同じローマの壁でもちょっと印象が違うはずです。(六田知弘) - 2005.07.06 中国・美の十字路展
-
東京六本木ヒルズの森美術館で始まった「中国・美の十字路展」に行ってきました。
これは、昨年、アメリカのメトロポリタン美術館で開催された中国展に展示された文物のうちの約半数に日本独自で選んだいくつかのものを加えて構成されており、時代的には後漢から盛唐までです。コンセプトとしては東西と南北の文化の交流とその精華としての盛唐の文化を一級の文物を通じて見せようというもので、シルクロードを経由する東西の交流のみではなく、北方の異民族と漢民族との南北の文化の交流にも焦点をあてた今までにない試みです。実は私もこの展覧会の企画にも少し関わらせていただき、昨年の夏に北京でポスターや図録の表紙、チラシなどに使う文物の写真撮影をし、寧夏回族自治区と甘粛省では、遺跡や町の撮影をしてきました。この時のことは、昨年この今週のトピックスにも書きましたのでご記憶にある方もいらっしゃることと思います。それで、今回約一年ぶりにそのときの文物と再会したというわけです。
美術館でガラスケースにいれられたそれらの文物達は北京の撮影室で見た時とはやはり印象が違いました。より晴れ晴れしく見えるもの、しょぼく見えるもの。さまざまです。そのなかで私にとっての印象が、場所が違っても変わらずに非常に鮮烈なものがひとつありました。それは、添付写真の銅製の振り向く鹿のオブジェです。展示品番号でいうと042番の「鹿形器」です。遼寧省の鮮卑族の貴族の墓から出土したものだそうですが、言い方が矛盾するようですが、なんという「リアルな抽象」でしょう。ちょっと私には想像をこえた造型感覚です。同時開催の中国現代アートの作家たちも真っ青というところでしょう。そのほかにも見るべきものがふんだんです。是非一見をおすすめします。
なお、森美術館は、9月4日まででその後は、MIHO MUSEUM(9月17日-12月15日)、九州国立博物館(2006年1月1日-4月2日)、東北歴史博物館(4月15日-6月18日)と続きます。(六田知弘)
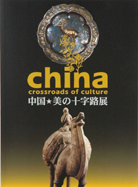

- 2005.06.29 清峯寺の聖観音像

先日、岐阜県の円空仏を見に行った話を書きましたが、そのときにロケハンとして撮影した写真のひとつをご覧いただこうと思います。
百体以上見たうちでもっとも好きなもものひとつです。飛騨の高山市国府町の清峯寺の聖観音像です。十一面千手観音像と善女龍王像とともに小さなお堂に祀られているもので、近くに住むおじさんに鍵を開けていただいて撮らせてもらったものです。まさしく木に宿った魂を円空がその手の鉈でなんのためらいもなく彫り出した。自然のなかに神仏を観るという縄文から延々と日本人の血の底流に流れる宇宙観。それを見せられたように思えました。(六田知弘)- 2005.06.22 テッペンカケタカ
-
二週間ほどまえになると思いますが、夜中12時過ぎに電灯を消して窓を開いて自宅の風呂につかっているとどこからかホトトギスの声が聞こえてきました。
チョチョッ、チョチョチョチョッ(テッペンカケタカ)というあの独特の声です。夜中のホトトギス。いままでに聞いたことがあるようなないような。わたしの家の周りの多摩丘陵は結構雑木の山林が残されていてさまざまな鳥の声が聞かれ、ホトトギスの声もたまに耳にします。しかし、夜にその声を聞くのははじめてかもしれません。よく響くその声を聞きながらこれはなんかの予兆なのかもしれないと、ちょっと気になりしばらく思いをめぐらしましたが、そんなのではないと根拠のない判断をしてその声を楽しむことにしました。
ホトトギスというとその近いなかまにツツドリやカッコウがいます。ツツドリは竹の筒を吹いたような低い鈍いこえでツツーッ、ツツーッと啼き、カッコウはもちろんカッコウ、カッコウと啼くのでこれら三種の鳥はそれぞれ全く違った声なのですが、姿はけっこう似ています。ツツドリといえば、一ヶ月ほどまえにこの今週のトピックス欄に小学六年生の頃に山に水晶を採りに行った帰りにずぶぬれになった話を書きましたが、そのときに土を掘りながらツツドリの声をはじめて聞いたことを思い出しました。そしてカッコウというとスペインのカタルニア地方のバヘス修道院を思い出します。堂守の家族がいるだけの荒れ果てたロマネスク様式の修道院の回廊で中世の血のにおいがするような兵士や鳥や怪物などをかたどった柱頭彫刻をひとり撮影していたときに、近くでカッコウがしきりに啼いていました。そんなことをぬるま湯につかりながらぼんやりと考えていると、このなかまには姿のほかにその声にもひとつの共通点があるように思えてきました。それは、その泣き声が人をこの世とは別のもうひとつの世界に引き込むような不可思議な作用をおよぼすということです。現実の世界と異界とをむすぶ媒体となるような鳥の声。やはりあぶないやつらなのかもしれません。(六田知弘) - 2005.06.15 盗まれた円空仏

雑誌の取材のついでに岐阜県の美濃地方と飛騨地方にある円空仏を見て回りました。
初っ端に関市の鳥屋市不動堂(とやいちふどうどう)に祀られていた円空仏19体と他2体が盗まれたというニュースを市役所で聞き、わたしが第一に見たいところだったので愕然としました。世に知られているものなので売れる訳もないのにバカなやつもいるもんだと呆れもしましたが、それ以上になさけなくなりました。円空仏ではないものもいっしょに盗み出したのだからおそらくだれかの指図によるものなんでしょう。
鳥屋市の不動堂は地元の人たちに花やご飯が供えられ今でも生きている仏さまなのに。円空さんを護ってきた地元の人たちのかなしみは察するに余りあります。よそものの私としても展示室での円空仏ではなく人々におまつりされている生きた円空さんを見たかったので残念でなりません。こんなことがあると円空仏に限らず、地元の人たちに祀られ、護られている仏像や古面など魅力あるものを見せてもらえる機会がどんどん減っていき、展覧会でガラス越しにしか見ることができなくなってしまいます。これではほんとうに情けない。早くお堂に帰ってくることをこころから願っています。
ところで、来週の21日(火)から神保町のギャラリー福果と表参道の インプレオ・ギャラリーでわたしの写真展「ローマ・時の壁」を同時開催します。ローマに行くたびに少しずつ撮ってきたもので、普通の建物の壁の一部分を切り取ったちょっと抽象絵画のような写真です。写真展が続いてもう飽きたというかたもいらっしゃるでしょうが、私の別の側面も(実は同じなんでしょうが)ご覧いただければと思います。(六田知弘)
◆六田知弘写真展「ローマ・時の壁」- ・ギャラリー福果 6/21-7/2(12:00-19:00:日休)
- ・インプレオ・ギャラリー 6/21-7/16(13:00-19:00:日月休)
- 2005.06.08 自然のものは自然に近い環境に
-
ギンブナ、アブラハヤ、モツゴ、シマドジョウ、ドジョウ、カマツカ。うちの屋外の水槽にいる川魚たちです。息子と、近所の程久保川と淺川が合流するところでビンドウやタモアミを使って採ってきたものです。かれらが来たのは、息子がまだ小学2年生のころだったので、まる6年経ったということになります。長生きしていると思いませんか。冬の間は底のほうでじっとしているので全く餌もやりません。春になって動き出しても餌は気づいたときにたまに少しだけやるだけで、夏に直射日光が当たらないよう覆いをかけてやるのと水が減ったら入れてやるというほかはほとんど手をかけることはありません。自然のものは、できるだけ自然に近い環境に置き、手をかけすぎない。それが長生きさせる秘訣なんだと中学生になった息子と確認しあいました。
そういえば息子が3歳のときうちの庭に蒔いたドングリも知らないうちにすくすく育ち、いまはもう3メートルを越えた若木となって新しいうす緑の葉っぱを枝のさきにいっぱいつけています。この木にドングリがなるのはいつなのか息子といっしょに楽しみに待っています。(六田知弘) - 2005.06.01 モノを「凝視」するということ
-
先日、ある雑誌の取材で作家の玄侑宗久さんにお会いするため、福島県三春に行ってきました。
写真を撮りながらお話をうかがったのですが、興味あるお話をいろいろしていただいたなかで特に印象に残ったこがひとつありました。それは、ものを見る時、「凝視」すると確かにある意味ではそのモノがよく見えるのだが、それは、そのモノのある一側面をみたことにしかならない。そして、それは容易に言葉やイメージに置き換えることができる。しかし、凝視とは別の見方、「うすらぼんやり」という見方も必要ではないか。それは、モノにその「全体性」において向き合うということであり、そのときには、言葉あるいはイメージに還元することができない、そのものの存在そのものを見ることとなる。そういう見方が重要なのではないか。というようなことでした。
そういうお話を聞きながらわたしは大徳寺龍光院にある牧谿筆と伝えられる「柿図」を思い浮かべていました。浅はかな私にどこまで理解できたのかこころもとないのですが、写真を撮るものとしてわたしが、ぼんやりと日頃考えていることとどこか重なるような気がしてひとり勝手に嬉しがってしまいました。(六田知弘) - 2005.05.25 雨に打たれて
-
先日、帰宅時に6時30分を過ぎていたのですが、あたりはまだ十分明るく、夏至まであと1ヶ月かなどと思いながら高幡不動の裏山を通って帰ることにしました。登りかけに地面にかすかな雨あとらしきものが見えたのですが、これくらいならだいじょうぶととっとと登っていきました。しかし、予測ははずれ、登りはじめて1分ほどで木々を打つ雨音がザーーッと長く聞こえるようになりました。でも雨水は私にはほとんどかからず、樹木の雨を受け止める力はたいしたものなんだなと悠長に感心しながらのんびりと登っていきました。しかし、頂上近くのこの前「日月山水図屏風」の太陽のような月が見えたところまで来た時には、大きな木の下にいっても大粒の雨水が私を容赦なくうってくるようになりました。これはまずいとつぎの大きな木をめざして水たまりをさけながら走ったのですが、もうすでにどの木も保水の限界を超えて、雨を避ける用はたたなくなっていました。傘も持たないわたしは、服のまま滝の下をくぐり抜けているようですっかりずぶ濡れになりました。もうこうなったら慌てても急いでも同じこと。そう思うとなんだか嬉しくなって思わず口元がゆるんでバカみたいにひとりで笑ってしまいました。こんなにずぶ濡れになったのはほんとうに久しぶりです。雨に打たれながら、小学6年生のときに友だちと3人で遠くの山に水晶を取りに行ってその帰りにやはり夕立ちにあい、ずぶぬれになりながら山道を駆け降り、途中で見かけた柿の実を盗み取って走りながら一口齧ったところがあまりに渋かったので思わず吐き出た。それでもなんだか雨を顔にうけながら走っているのが愉快に思え、友だちもいっしょにげらげら笑いながら駆けている。そんな状景を思いだしました。雨にぬれて気分は逆に晴れました。(六田知弘)
- 2005.05.18 心の隙間をうめる多度式鏡
-

先日、東京のある古美術店で直径8cmほどの青銅の鏡を見かけました。
表面は錆びていて状態がよくなかったせいで、一見、紋様のない素文鏡に見えました。しかし、その極めて薄作りで小さく細い鈕(つまみ)のかたちから、平安時代の多度式鏡だということはすぐにわかりました。多度式鏡は、出羽三山神社で羽黒鏡の写真を撮らせてもらったときに数枚見て、そのときからその魅力に引かれていました。わたしは、それを見つけるとほとんど同時に手にとっていました。周縁の三分の一はボロボロと欠け落ち、一ケ所大きく折り目がついていました。紋様もふつうの光ではどういうものかよくわかりません。光のあたり具合をいろいろ変えてみてやっとのことで二羽の鳥が、草のうえを飛び交う紋様だということがわかりました。先日の写真展が終わってから2、3日、どういう訳かわたしのこころにひとつの穴がぽっかりと開いたようでひゅうひゅうと風が吹き抜けていく感じがしていました。その穴にこの鏡がぴったりと大きさやかたちが合うように思われ、なんだか妙な感覚に捕われました。この鏡はわたしの許に来るためにここに今あるんだと思ってしまったのです。またいけない病気が発症してしまったということは、そのときにもわかりました。その鏡は思ったよりずっと安価でした。でもかせぎの少ない私ににとってはそんな価格でも一大決心が必要です。苦しみます。しかし、それがわかっていても止められないのがこの骨董病の特徴なのです。私もだいぶ病状が進行してきたようです。今はこの病気も私の仕事に必要な糧なのだと理由をこじつけたりしながら病と共にいきていくしかないのかもしれません。(六田知弘) - 2005.05.11 感謝

三越での「巡礼・日本美」展がおかげさまで盛況のうちに終えることができました。
これも、ほんとうに多くのかたがたに暖かいご協力をいただくことができたからこそと、みなさんに深く感謝致します。思えばなかなか厳しい道のりでしたが、なんとかかたちにすることができたのは、私を支援してくださったかたがたがいたからで、好きなことばかりをさせていただけてわたしはなんと幸せ者かとつくづく思っています。遠くから、近くから私を助けて下さったみなさんの顔が思い浮かんできます。ほんとうにありがとうございました。6日間と短い期間でしたが、それを終えた今はどっと疲れが出てきました。しかし、展示最終日の夜は、蒲団に入ってもなかなか寝付かれませんでした。わたしには、めずらしく次の写真展の展開をことが頭をめぐり、眠ることができなかったのです。私も少しづつ前向きに、ポジティブにものごとを考えることができるようになってきたのかも知れません。ほんとうに「おかげさま」です。(六田知弘)- 2005.05.03 本日より開催「巡礼・日本美」展
-
いよいよ今週の3日(火)から8日(日)まで私の「巡礼・日本美」展」を日本橋三越本店本館特選別室で開きます。
今回のものは日本の古美術を撮ったもので、「和樂」などでご覧いただいたことがあるのも多いと思いますが、雑誌や図録などの印刷物とは大きさも色の調子もかなり違い、見た時の印象は、別の写真ではないかと思える程の差があるのではないでしょうか。私自身、実際プリントをしてみてこれにはいささか驚いております。今回のプリントは、「雲岡」展と同様、トリミングや色の調整などすべて私自身がやったもので、私の「オリジナルプリント」といえるものです。
そういう意味でもこのゴールデンウイークの期間中、是非会場に足をおはこびいただきたいと思います。わたしは、基本的には、毎日会場におりますのでお声をおかけいただければ嬉しいです。お待ちしております。(六田知弘) - 2005.04.27 日月山水図の太陽とは

先終末、都内に出た帰り、まだ薄明かりが残っていたので高幡不動の裏山の小道を登って家に帰りました。空にはわずかな光が残っているとはいえ、さすがに木々の生い茂った道はかなり暗いのですが、そのためか、かえって嗅覚が敏感になったようで若葉が発散するにおいをなぜか懐かしく感じながら登っていきました。急な坂道を登り切ったところまで来た時、あたりがいきなり明るくなりました。小さな二つの尾根の樹木のすきまから鈍色の群青の空が見え、その真ん中に満月に近い十四番目の月がこうこうと山肌を照らしだしていました。わたしは、瞬間、今プリントしている金剛寺の日月山水図屏風の春夏景の部分を思い出しました。そこに描かれているのは、もちろん月ではなく太陽です。しかし、日月山水図屏風の太陽はまぎれもなくこの鈍い金色です。
今、「巡礼・日本美」展のプリントの真っ最中です。そのポスターに日月山水図屏風の部分を使わせてもらいました。印刷とは一味も二味も違う私のプリントでその日月山水図屏風の太陽を是非ともご覧いただきたいものだと思います。(六田知弘)- 2005.04.20 個展の準備:プリントについて
-
いよいよ5月3日からの「巡礼・日本美」展が迫ってきました。
いま、展示用のプリントの真っ最中です。それと並行して図録の印刷の制作作業もしていて、さきほど再校のチェックをしてきました。やはり、いつものことですが、なかなか簡単には思うような色はでてくれません。あとは、なんとかいい印刷になってくれるよう印刷所のかたにお任せするしかありません。祈るような心境です。その点、展示プリントはすべてが私の手にゆだねられています。気力と体力が勝負で、いささか疲れますが、良くなるのも悪くなるのもすべて私次第と言うところはある意味では気楽かも知れません。あと二週間、がんばります。(六田知弘) - 2005.04.13 個展「巡礼・日本美」GW開催
-
「雲岡」展がこのまえ終わったばかりなのに次の「巡礼・日本美」展まであと一ヶ月を切りました。いまは、だいたいの展示作品のセレクトとフレームの発注を終え、これからいよいよプリントにとりかかろうとしているところです。
点数は、小さいものも多いので60点近くにもなり雲岡のプリントのときのことを考えるとたいへんですが、なんとか最高のプリントでみなさんにご覧いただけるようがんばりたいと思っています。
ところで、最近わたしは、もっぱら美術品の写真を撮っていますが、このことに関して、まえから考えることがあります。それは、美術品を撮った写真の作品性についてのことです。はたして美術品の写真は、写真家の創作活動といえるのかということです。美術品のすがたを忠実にフィルムに写し撮る。それにはもちろんある一定以上の技術が必要で、ある意味では、職人的な作業だといえるでしょう。そこには、一見写す側の個性や思想などはいる余地などないように思えます。もちろん、美術品を風変わりな場所に置いたり、着色したり、レンズで歪めてみたり、さまさまな細工をしてその美術品を素材に創作のようなことをすることも可能です。しかし、わたしはそのような撮り方はしません。ですからそれは、創作活動ではないのかもしれません。それでもかまわないと私は考えます。
創作活動であろうとなかろうと私は、その美術品と向き合い、それが発する言葉ではないなにかを感じ、それをフィルムに定着させること。そこにわたしは喜びを感じているのですから。(六田知弘) - 2005.04.20 個展の準備:プリントについて
-
いよいよ5月3日からの「巡礼・日本美」展が迫ってきました。
いま、展示用のプリントの真っ最中です。それと並行して図録の印刷の制作作業もしていて、さきほど再校のチェックをしてきました。やはり、いつものことですが、なかなか簡単には思うような色はでてくれません。あとは、なんとかいい印刷になってくれるよう印刷所のかたにお任せするしかありません。祈るような心境です。その点、展示プリントはすべてが私の手にゆだねられています。気力と体力が勝負で、いささか疲れますが、良くなるのも悪くなるのもすべて私次第と言うところはある意味では気楽かも知れません。あと二週間、がんばります。(六田知弘) - 2005.04.13 個展「巡礼・日本美」GW開催
-
「雲岡」展がこのまえ終わったばかりなのに次の「巡礼・日本美」展まであと一ヶ月を切りました。いまは、だいたいの展示作品のセレクトとフレームの発注を終え、これからいよいよプリントにとりかかろうとしているところです。
点数は、小さいものも多いので60点近くにもなり雲岡のプリントのときのことを考えるとたいへんですが、なんとか最高のプリントでみなさんにご覧いただけるようがんばりたいと思っています。
ところで、最近わたしは、もっぱら美術品の写真を撮っていますが、このことに関して、まえから考えることがあります。それは、美術品を撮った写真の作品性についてのことです。はたして美術品の写真は、写真家の創作活動といえるのかということです。美術品のすがたを忠実にフィルムに写し撮る。それにはもちろんある一定以上の技術が必要で、ある意味では、職人的な作業だといえるでしょう。そこには、一見写す側の個性や思想などはいる余地などないように思えます。もちろん、美術品を風変わりな場所に置いたり、着色したり、レンズで歪めてみたり、さまさまな細工をしてその美術品を素材に創作のようなことをすることも可能です。しかし、わたしはそのような撮り方はしません。ですからそれは、創作活動ではないのかもしれません。それでもかまわないと私は考えます。
創作活動であろうとなかろうと私は、その美術品と向き合い、それが発する言葉ではないなにかを感じ、それをフィルムに定着させること。そこにわたしは喜びを感じているのですから。(六田知弘) - 2005.04.06 春と修羅
-
序
わたくしといふ現象は 仮定された有機交流電燈の ひとつの青い照明です
(あらゆる透明な幽霊の複合体) 風景やみんなといっしょに せわしくせわしく明滅しながら
いかにもたしかのともりつづける 因果交流電燈の ひとつの青い照明です(ひかりはたもちその電燈は失われ)・・・・・
宮沢賢治の「春と修羅」の序文の書き出しです。「春と修羅」は若いころの私の座右の書でした。ヒマラヤのシェルパの撮影のときにも文庫本のぼろぼろになった一冊をいつもカメラと一緒にバックに入れて持ち歩いていました。もし、いまのわたしに世界観とよべるものがあるのだとしたら、それは、間違いなくこの「春と修羅」からの影響が大きかった言えるでしょう。今日は、ひさびさにこの「わたくしといふ現象は・・・というフレーズが繰り返し頭の中に浮かんできました。ひとつの魂がこの世から離れようとしています。無能のわたしはただただお経のようにこのフレーズを唱えることしか出来ません。(六田知弘) - 2005.03.30 埴輪の腕
-
先日奈良の古美術店で埴輪の腕を見つけました。左腕の肘から先の部分で7~8cm程の小さなものです。親指はありますが、他の四本の指の先は欠損しています。おそらくもともとそれらの指は作っていなかったのだと思いますが親指の曲がり具合とその付け根の筋肉のつき具合、そして腕全体のぽちゃっとした感じがなんとも愛らしく安価なこともあって購入しました。どういう埴輪の腕だったのかこれだけではほとんどわかりません。その小さな掌に自分の親指をあててみます。するとなんとも懐かしい感触が伝わってきます。それは、生まれたばかりのわが子の手を恐る恐るはじめて握った時の感触でした。息子も今度中学生となり、その掌もわたしのものとほぼ同じになりました。(六田知弘)
- 2005.03.23 美を見い出す日本の美学
-
渥美とされる壷を撮影しました。
高さ45cm、径40cmぐらいのパンパンに張った球型にちかいボリューム感あふれる見事な大壷です。須恵器のような白っぽい肌で、肩には、フリモノが一面に付着して、緑色の自然釉がこれまたはげしく流れています。下半身には輪積みあるいは紐造り成形の痕が見られ、胴部には叩締めの痕跡も見受けられます。そして少しですが、全体に傾きひしゃいでいます。よく言われることですが、これは人と自然の共同作品に他なりません。もちろんこれらの壷は、あくまで実用品としてつくられ、また使われてきたのであって、当初はそこになんら美を見い出すようなことはなかったはずです。しかしなぜ、いまの我々は、ある意味ではこんなきたない、崩れた、よごれた器物を見て感動し、そこに美を見い出すのでしょう。こんなところに美を見るのは、日本だけのことかも知れません。少なくとも中国ではありえないことではないでしょうか。
中国のやきものは、あくまで人が自然をコントロールして人知のうちに作り上げられます。よく宋代のすぐれたやきものに神品という形容詞がつけられますが、これも計算された究極の人の技です。日本ではお茶や生け花の世界で昔からこうした古窯のものに美を見い出し、珍重されてきました。それに、わたしのようなお茶やお花の全くの門外漢でもそこに強い引力を感じることは確かです。しかしいったいこんなところにひきつけられ、美を見い出す日本の美学とはなんなんでしょう。おそらくそれは日本人がもつ自然と人との独特の関係のありかたに起因することなのだと思います。うまく表現できませんが、私には、相対し征服すべき対象としての自然ではなく、自然のなかに生まれ、生きている存在としての人間の姿をわれわれ日本人は古い壷を見て触れることによって感じ取っているのではないかという気がするのです。(六田知弘) - 2005.03.16 ほんとうの「目利き」
-
先日、雨の中、葉山にある神奈川県立近代美術館で開催されている「矢代幸雄資料展」に行ってきました。矢代幸雄というのはの奈良にある大和文華館の蔵品を近鉄の依頼で集めた美術史家ですがこの資料展には、ボッティチェリ研究をはじめ彼の多くの著作とともに彼が身近において愛玩した古美術品も十数点展示されていました。京都の古書店で見つけたという虫食いだらけの平安の紫紙金泥経の見返し、松永耳庵から譲られたという粉引の馬上杯、矢代の師ベレンソンから贈られた中国南北朝の鍍金の獅子、日本にいた東洋学者サンソムからもらったという北魏の二仏並座の石像、ドイツのキュンメル旧蔵でウイグル自治区ヤル・ホト出土の麻布に描かれた菩薩像断片など・・・。私などただただうなるばかりでした。人からもらったり譲られたりしたものが多いのににどうしてここまでひとつの通底した美学に貫かれた魅力あるものが彼のもとに集まるのか。ほんとうの「目利き」というものはこういうものだと一人で納得しながら二時間かけて帰宅しました。(六田知弘)
- 2005.03.09 5月の個展に向けて

3月4日に繭山龍泉堂での写真展「雲岡」が終了しました。
おかげさまで大成功でした。お忙しい中おいでいただいた方々、そして、さまざまな場面で写真展成功のためにアドバイスやご協力いただいた多くの方々に対しほんとうに心より感謝いたします。私の写真とぴったりとあった最高の会場を使わせていただけたので、みなさんにはゆっくりと落ち着いた気分でご覧いただけたことと思います。私としましては、ここで一息ついて好きな骨董をいじくっていたいところなのですが、お買い上げいただいた雲岡のプリントの制作と5月3日からの日本橋三越本店での「巡礼・日本美」の準備にすぐにとりかからねばなりません。この写真展は、会場の質が違うので雲岡とは少し違った雰囲気のものになるでしょうが、これもまたきっと多くの方々にお楽しみいただけるものと思います。乞う御期待を!(六田知弘)
3月10日(木)より、会場をインプレオ・ギャラリーに移しまして、引き続き六田知弘写真作品「雲岡」をご覧いただけます。詳細はインプレオ・ギャラリーにあります「雲岡(インプレオ・バージョン)」のページをご覧ください。
- 2005.03.02 雲岡展は3月4日(金)まで
-
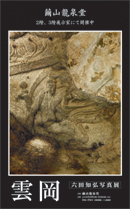
また今週も京橋の繭山龍泉堂で開催中の私の写真展「雲岡」についてになってしまいますことをお許しください。いよいよ後半に入りましたが、いままでの印象として第一にあげられるのは、おいでいただいた方々には、中国美術の研究者、コレクター、古美術商、会社の経営者、アーチスト、美術館の方、建築家、出版関係者そして一般の会社員や主婦の方などさまざまな分野のかたがいらしゃるのですが、皆さんほんとうにお好きなんだなということです。古美術品については私もある意味でちょっと病的なほどにに好きなのですが、同じ病気にかかっている方がこんなにいらっしゃるとは思いませんでした。
優れた古美術品の前では、同じ病気の者どおし、社会的立場の違いなど関係なくみんな子供の目になって語り合うことができます。これは、最高のよろこびです。こんな触れあいの場を与えて下さった繭山龍泉堂の方々にほんとうに感謝しております。雲岡展は3月4日(金)までです。私は毎日会場におります。同じ病気の方もそうでない健康な方々も是非おいでいただき、普段とはちょっと違った空間で語り合えれば最高です。(六田知弘) - 2005.02.23 個展「雲岡」、始まりました
-
2月21日、写真展「雲岡」の展示作業をしました。東京 京橋の古美術店「繭山龍泉堂」の2、3階をお借りしての展示ですが、2階を「大いなる仏」、3階を「祈りの空間」と題しました。2階には、主に外から見ることができる曇曜五窟を中心とした大きな仏の写真を、3階には雲岡石窟群の無数の窟のうすぐらい内部を長時間露光をかけて自然光で撮影した小さな仏、菩薩、飛天などのすがたです。この写真展は2月22日から3月4日までで27日の日曜日を除く毎日11時より6時まで(入場は5時30分まで)開場しています。オリジナル写真や特製ボックス入りの作品集、ポストカードなども会場で販売しています。もちろん入場は無料ですのでお気軽にお立ち寄りください。わたしは、基本的には毎日会場にいる予定です。みなさまのご来場をお待ちしております。(六田知弘)
- 2005.02.16 個展、来週火曜日スタート
-
東京京橋の古美術店「繭山龍泉堂」でやらせていただく写真展「雲岡」の展示写真のプリントもいよいよ終盤にさしかかりました。大判のプリント作成作業が大変なことはある程度は予想はしていましたが、実際は予想をかなり上回るハードさです。最後の詰めのもうひとがんばりの最中です。(六田知弘)
- 2005.02.09 個展の準備
-
昨日、今日の二日間、家にこもってプリンターとまさに格闘していました。
22日からの「雲岡」展のためのプリントですが、いつもとプリンターもペーパーの種類もサイズも違うため色の調子を出すのが難しく結構悪戦苦闘しています。長引いた風邪も治ったことだし、とにかく雲岡の石窟のまえに立った時、私が感じたあの空間の空気と光りを写真展に来て下さったみなさんに感じていただけるよう、ここ数日はプリントに集中するしかありません。(六田知弘) - 2005.02.02 個展「雲岡」が22日から始まります
-
2月に入り、東京京橋の古美術店、繭山龍泉堂での写真展「雲岡」展が迫ってきました。
写真の構成はほぼ決まり、これからいよいよプリント作業にはいるところです。プリントのサイズは大判や全紙を中心にかなり大きなものにする予定です。先日試作としてで本番と同サイズのものを数枚作ってみました。自分でいうのもおかしいですがなかなかの迫力で、石の肌触りや空気感まで感じられ、思いもよらぬほどの臨場感を感じました。この写真展ではみなさんに雲岡の大いなる仏を仰ぎ見し、うすぐらい窟のなかに浮かび上がる無数の小さなほとけや天空を舞う飛天たちをリアルなものとして感じていただけたらと思っています。2月22日からの「雲岡」展、お立ち寄りいただくことお待ちいたしております。(六田知弘) - 2005.01.26 写真を撮るということ
-
私にとって古美術品の写真を撮るというのは、どういうことなのか考えました。
モノが発する様々な波長、波形のエネルギーのようなものを感じ取り、それをフィルムや紙上に定着させること。ただそれだけのことなのだろうと思います。そのためにはもちろん技術やそのものに対するある程度の知識は必要です。しかしそれよりモノが発するものを感じ取る受信装置として撮影者の感度が問題となってくると思います。いかに幅広いレンジを持ち、いかに微妙な波長を感知できるか。それも言葉に置換できるような観念の位相ではなくて。あたりまえですがそれは容易なことではありません。名品だといわれるものを前にして、あるいは自分がよいものだと思いこんでいたものを前にして、どう撮ったらよいのかさっぱりわからなくてファインダーを覗いては腕を組み、悩み苦しむときもしばしばです。しかしいまの私にはそうしたモノと自分とのせめぎあいのなかからモノが発する何かを感知し、写し留めることができたと感じたときの満足感に代わるものはないのです。とにかくもっともっといいものを撮るチャンスがほしいのです。(六田知弘) - 2005.01.19 東京国立博物館「唐招提寺展」
-
先週に続いて仏像のことで恐縮ですが、先日、東京国立博物館の「唐招提寺展」に行って金堂の廬舎那仏を見てきました。
予想以上に唐招提寺の堂内で見るものとは大きな印象の違いがありました。三千世界の中心に坐すという大いなる佛である廬舎那仏を象徴する千体もの化仏をつけた大光背がないこと。あの美しく反った大きな金色の蓮弁をもつ台座がないこと。この二つが大きく印象をちがえた物理的な原因であることはすぐわかります。しかし、それ以上に光がちがうのです。唐招提寺の金堂の堂内の仏像は、空から(上方)の直接的な光ではなく一度地面にあたった光がはね返る反射光によって下方からから照らしだされます。それによって金色の大いなる佛が薄暗い背景からうかび上がるのです。そこに我々は仏の世界を観じるのだと思います。
もちろん今回は博物館で見るのだから仕方ないのですが、今、全面的な解体修理をしている金堂のことを考えるとちょっと心配になってきました。この廬舎那仏や千手観音、薬師如来そして四天王などの諸像が修理後のお堂にもどった時、あの包み込むような光でふたたびそれらの仏を仰ぐことができるのだろうかと。(六田知弘) - 2005.01.12 當麻寺の持国天
-
正月3日から6日まで仕事で奈良県の當麻に行き、當麻寺(たいまでら)の金堂の仏像を拝観しました。そこには、私が子供のころから祖父に連れられて来たり、あるいは小学校からの写生会のときに覗いたりして慣れ親しんだ彌勒座像と四天王像があります。多門天は鎌倉時代の後補ですが、塑像の彌勒と脱活乾漆の増長天、広目天、持国天は白鳳期のものです。その四天王は法隆寺の金堂の飛鳥期のものと、東大寺戒壇院などの天平期のもののちょうど中間に位置するような様式といえるのでしょうが、2メートルはゆうに超える堂々たる体躯で、精悍な顔にちりちりとカールした顎鬚を生やしてマントを肩からかけ、その襟を高く立てているのが特徴です。堂内はライトなどはあてておらず、うす暗いのですが、やわらかい自然光で見ることができるのがありがたい。本来、仏像は自然光かさもなければ灯明のあかりなどで接するのが自然なのでしょうが、近ごろはどこのお寺も拝観者への便宜のためか下手なライティングで興醒めなことが多いようです。しかし、ここは光線も佛像の配置も私の子供のころと全く変わっていないように思えます。それにしても、10年近く前に奈良国立博物館で見たライトアップされた持国天とこの堂内で見る持国天とが同一のものに見えないのは仕方のないことなのでしょう。私は、いつかこれらの像をこの堂内で、この光で撮影する機会がほしいものだと強く思いました。(六田知弘)
- 2005.01.05 雪の新年
-
大晦日の昼過ぎから夕方にかけて東京で雪が降りました。
私の住む多摩丘陵では解けるひまもなく降り積もり、5~6センチの積雪となりました。大晦日の東京での積雪は二十数年ぶりだとのことでですが、私にはその記憶はありません。もしかしたら私がヒマラヤの村に滞在していた年なのかもしれません。
私は二十代の後半、写真をとるためにネパールヒマラヤのシェルパの村に延べ18ヶ月ほど滞在していたことがあります。ある年の元旦を標高4000メートルにある小さなゴンパ(ラマ教の寺院)で迎えました。人の住む集落から獣道のような細い小道を30分ほどほとんど直登した急な斜面にへばりつくようにそのゴンパは建っています。私は暮れからその寺の本堂にひとり寝泊まりさせてもらっていました。暖房もない標高4000メートルの冬の夜の堂内の空気はまさに凍てつき、菜種油の灯明のほのかな明かりがわずかに私のこころを暖めてくれるばかりです。耳のなかでは私自身の血液が流れる音がシンシンと聞こえました。それほどの無音の世界。私は服もズボンも靴下もはいたまま寝袋にもぐり込みました。翌、元日の朝、真っ黒な堂内に扉の隙間の白い光の線があざやかに見えました。外に出ようとして、その扉を内側から開けようとしても重くてなかなか開きません。雪でした。昨夜のうちに降り積もった雪が扉を阻んでいたのです。私は全体重をかけてなんとか出るだけの幅を押し開けたのですが今度は靴が見当たりません。雪に完全に埋もれてしまっていたのです。こんな雪の新年をえた時もありました。(六田知弘)